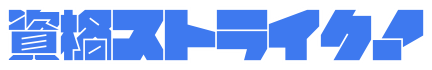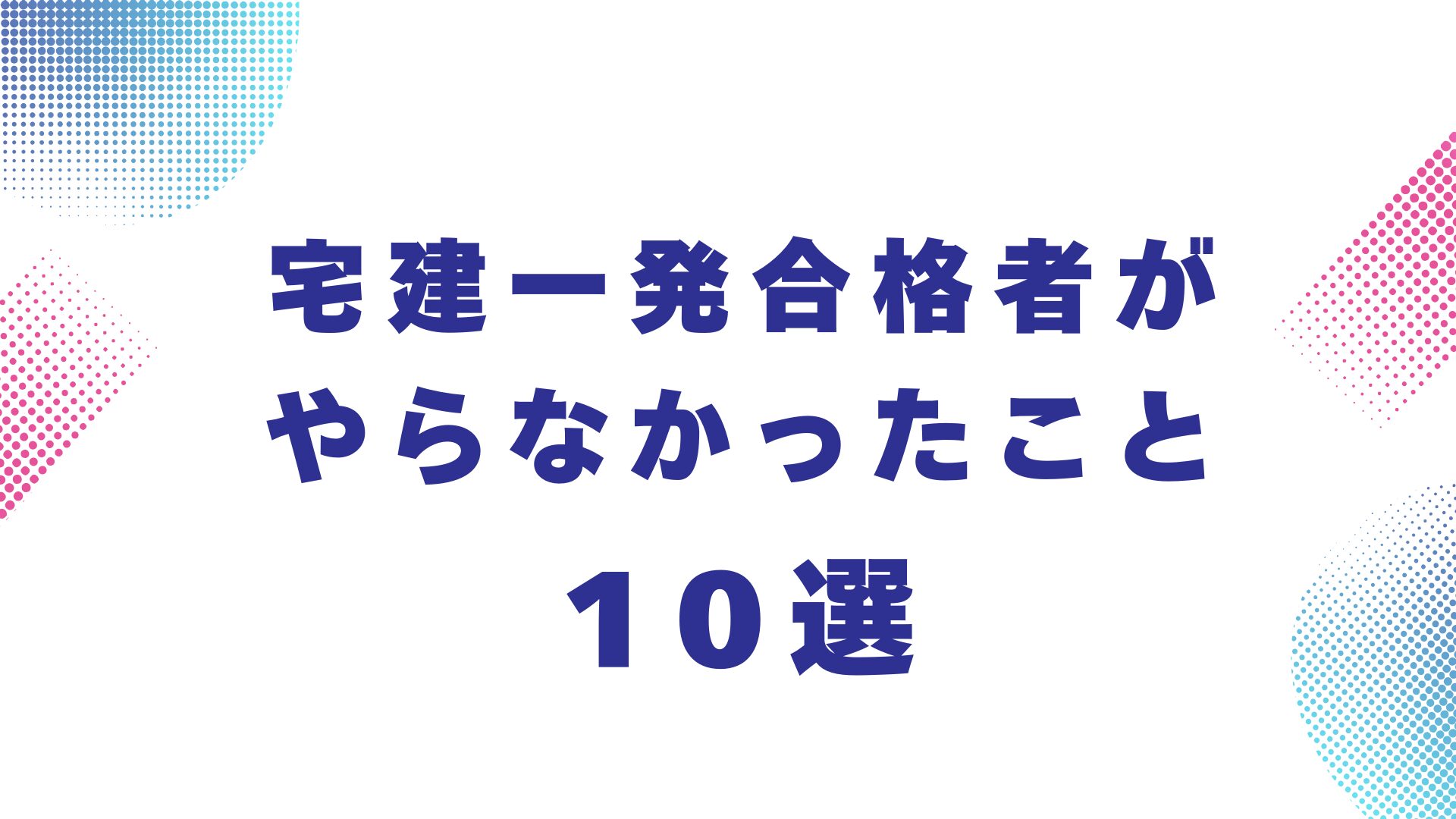どうも、私は当ブログの管理人、ぞねぞうと申します。
私は、2024年度の宅建試験に挑戦し、50点中満点中44点の得点で一発合格を果たすことが出来ました。
宅建試験の学習法については、やった方がいいこと、逆にやらない方がいいこと等々、ネット上にも様々な意見が飛び交っています。
そこでこの記事では、一発合格を果たした私の経験を元に、「やらなかったこと」によって合格に結びついた10項目をピックアップしてみました。
あくまでも私の個人の体験となっていますが、宅建試験合格を目指す皆さまの参考になればと思っています。
宅建一発合格者がやらなかったこと 10選
①周辺知識を大量に暗記する
私は、周辺知識を大量に暗記するという勉強法は行いませんでした。
周辺知識とは、過去問で問われた知識に関係している知識のことであり、その問題では直接問われてはいないものの、同時に押さえておくべき知識のことです。
宅建の本試験では、過去問の周辺知識を聞いてくる問題が数多く出題されるため、周辺知識を大量に覚えることが合格に繋がると言われています。
私も、受験生時代には周辺知識を増やそうと頑張っていましたが、今一つ腑に落ちないことがあり、あまり上手くいきませんでした。
周辺知識という言葉が漠然としていて、どこからどこまで覚えたらいいのか分からなかったのです。
それよりも、「テキスト&過去問の重要な知識を押さえ、それらをテキストに一元的に集約していく」という方法で学習を進めていきました。
そして本試験ではそれらの知識が何問も出題され、見事に一発合格を果たすことができました。
宅建試験では、テキストの基礎知識にアレンジを加えた問題が何問も出題され、それらを確実に取り切れば合格できるようになっています。
試験で求められていることは、知識の絶対量ではなく、基礎知識の正確な理解と現場思考の能力なのです。
ここで、周辺知識という言葉の持つ響きが障害となってくるのです。
周辺知識という言葉を誤解すると、覚えるべき知識の範囲が曖昧になってしまうのです。
特に、出題頻度の低いCランクの知識まで手を広げるようとするあまり、肝心のAランクの基礎知識にポッカリと穴が開くという、「知識のドーナツ化現象」が起こりやすいのです。
こうなれば、ますます合格は遠のいてしまうでしょう。
何よりも大切なのは、テキストに載っているレベルの基礎知識をしっかりと押さえておくということなのです。
②過去問の解説欄に周辺知識を書き足す
宅建試験における周辺知識とは、過去問で問われた論点に関連している知識のことです。
宅建の本試験では、過去に出題された問題と全く同じ問題が出題されるケースは少なく、過去問の周辺知識を聞いてくる問題が多く出題されると言われています。
この周辺知識を過去問を解きながら確認し、それらを解説の余白に書き加えてオリジナルのテキストのように仕上げていく、というやり方をしている人をネット上でチラホラ見かけました。
しかしながら、私はこの方法を取り入れることはありませんでした。
なぜなら、私は受験指導の素人だからです。6月下旬に勉強を始めたばかりの初学者なのです。
周辺知識を過去問の解説欄の余白に書き込むといっても、どの周辺知識をどれだけ書き込んだらいいのでしょうか。
そもそも、初学者に周辺知識の出題頻度など分かるはずが無いのです。
現実的には、テキストに載っているまとめ表などの知識を参考書の余白に書き写す、という作業になってしまうでしょう。
だとしたら、テキストそのものに付箋を貼ったりマーカーを引いたり等のカスタマイズを加え、それを何度も見返した方が手っ取り早いと思ったのです。
テキストこそが、受験指導のプロが精魂をこめて作り上げた重要知識の塊ですからね。
このテキスト中心の学習方法はピッタリとハマり、学習の大きな効率化に繋がりました。
③テキストを辞書代わりにする
ネット上では、過去問の解説を読んでも分からないときだけテキストを参照するという、いわばテキストを辞書代わりに使うことを推奨する意見もよく見かけます。
テキストを読むのは時間がかかるので、過去問の解説欄の余白に適宜書き込みを行いつつ、過去問を何度も見直すという、過去問中心の学習を勧めているんですね。
中には、本試験の会場には過去問だけ持っていくという人もいます。
この方法に関しても、私は取り入れることはありませんでした。
それよりも、間違えたこと・曖昧なことは常にテキストに戻って確認し、付箋やマーカーで印をつけるなどしてカスタマイズし、後で何度も見返すという、いわばテキスト中心の学習を進めていました。
そのテキストを、本試験の会場にも持ち込んで見直しを行うことで、高得点を取ることができました。
宅建試験のテキストは、各資格スクールが長年の指導経験で培ったノウハウをもとに、魂を込めて作られています。
重要事項を整理するための図解や比較表はプロが作っただけあって非常に分かりやすく、初学者が作ったまとめノートでは太刀打ちができないでしょう。
それらを活用すれば、短時間で効果的な見直しができるのです。
テキストを辞書代わりに使ってほとんど見返さないということは、大変もったいないことをしているのです。
以下の記事でも、テキストに書いてある基礎知識を元にした問題が大量に出題されていることを検証しています。
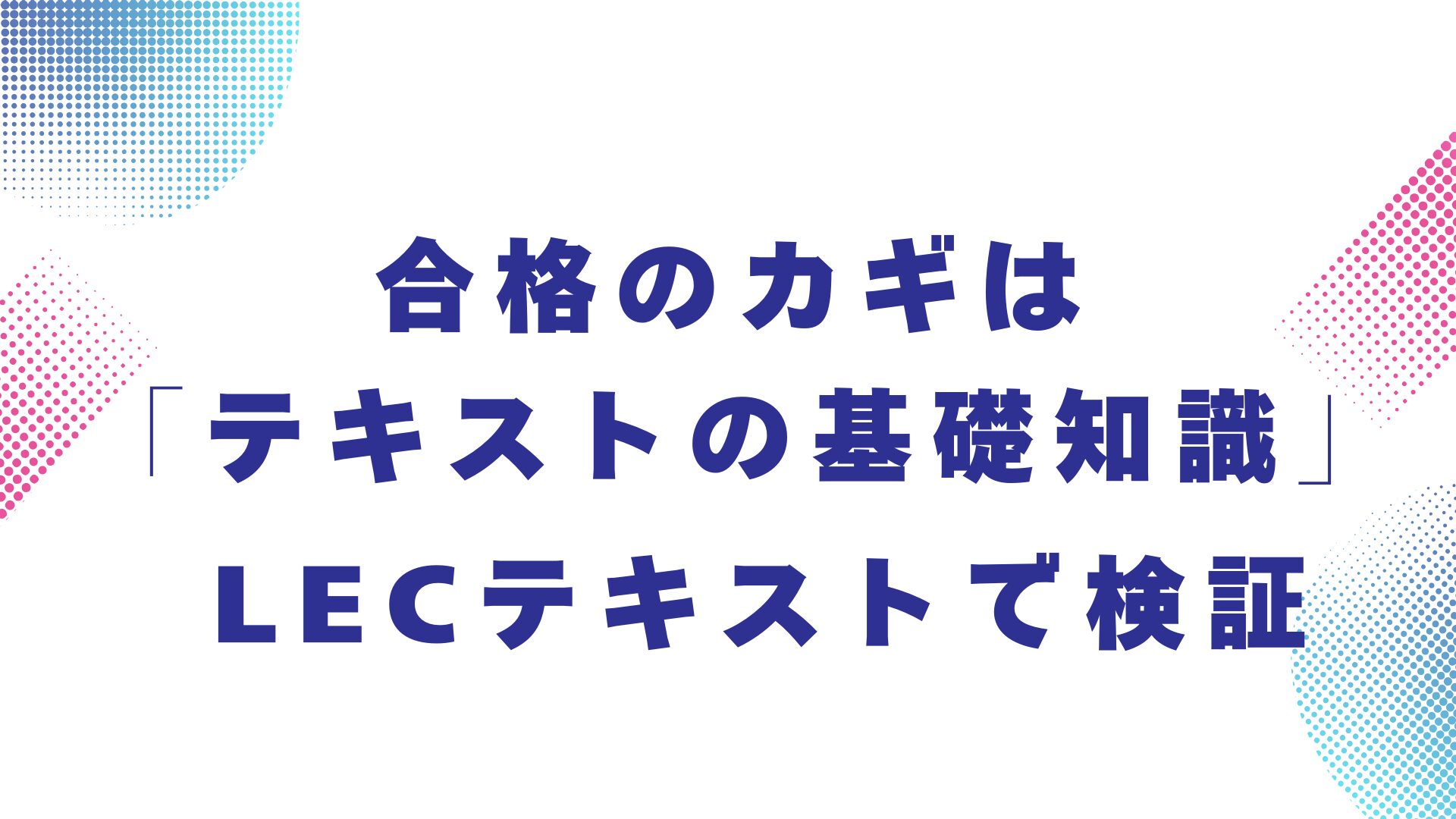
④動画をテキスト代わりにする
最近は、受験生の学習環境も著しく向上しています。
それぞれの資格スクールは競い合って質の高い講義を提供し、YouTube上では有料級の良質な講義を無料で発信してくれる講師もいます。
こうした講義の動画は理解を進める上ではとても有益なのですが、テキストの代わりにはならないことを留意しておく必要があります。
動画の場合、聴覚と視覚に印象づけることで理解の助けになるのですが、見直したい個所に戻るのに時間がかかり、復習の際に使いづらいという弱点があるのです。
動画よりもテキストの方が、まとめ表や図解で整理した情報を素早く見直せるため、復習の際には便利なのです。
本試験までに何度も復習をすることを考えると、テキストは無くてはならないものなのです。
このことは、どの資格スクールも必ずテキストを提供していることからも分かります。
「動画があればテキストは不要」という意見には、ハッキリと異を唱えたいと思います。
⑤1冊の過去問題集を10回以上繰り返す
ネット上では、1冊の過去問題集を10回、20回と繰り返し、その内容を暗記することを勧める意見が散見されます。
中には、確実に覚えるまで毎日復習し、進捗をスケジュール表で管理することを推奨している人もいます。
私は、この方法を取り入れることはありませんでした。
こんなことをしていたら、復習だけで受験勉強が終わってしまうと思ったからです。
こうするよりも、テキストをベースに暗記する箇所を明確化し、それらを何十回も反復するようにしていました。
結果として、基礎知識の確実な定着につながり、一発合格を果たすことができました。
過去問題集を10回以上繰り返すことの問題点は、初見の問題に対応できなくなるということです。
周回を重ねるうちに思考訓練としての効果が薄れ、「問題と答えのマルバツを何となく覚えているだけ」という状態に陥りやすいのです。
宅建試験において重要なのは、基礎知識の正確な理解と現場思考の能力です。
そのためには、過去問題集をそのまま覚えるのではなく、テキストに立ち返って問題を解く上での基本ルールを抽出していくのです。
このようにして体系的に基礎知識を身に付ければ、やがてそれは現場思考の能力に結びついていくのです。
私は、過去問題集1冊につき、多くても4周分しか繰り返していません。
ウォーク問も、ちゃんと問題を解いたのは2周分だけで、後は2回ほどサラっと全体を見直した程度です。
それでも、情報をテキストに一元化するようにすれば、十分に知識の定着は出来るのです。
⑥自分だけの「オリジナルまとめノート」を作る
「書く」という作業は時間のムダになると思ったので、自分だけのまとめノートを作ることはしませんでした。
初学者のうちは重要な知識とそうでない知識の見分けがつかず、何をどうまとめたらよいかが分からなかったからです。
その代わりに、私は資格スクールのまとめ講義やレジュメを活用しました。
プロの力に頼った方がよっぽど効率がいいと感じたからです。
実際にそうすることで、学習をスムーズに進めることが出来ました。
もちろん、直前期ならば、重要知識を見分ける能力が身に付いているため、まとめノートを作ることにも一定の効果はありますが、初学者のうちは効率が悪いでしょう。
⑦1番目の選択肢が正解だと思ったら、2番目以降は読み飛ばす
宅建試験は、ひとつの問題につき4つの選択肢の中から正解の番号を選んでいく選択式の試験です。
問題数は50問あり、それを2時間以内に解答しなければなりません。
そこで、ネット上では数々の時短テクニックが取り上げられています。
その中でも、「1番目の選択肢が正解だと思ったら、1番目をマークして2番目以降を読み飛ばす」ということを推奨する意見がチラホラ見かけます。
こうすることで、時間の短縮に繋がるということなんですね。
それでも、私はこの方法を取り入れることはありませんでした。
敵(試験委員)もさるものであり、1番目の選択肢を正解に見せかけるひっかけ問題も出てくるでしょうし、ケアレスミスも防げないと思ったからです。
本試験では、全ての選択肢を読み飛ばすことなく吟味し、十分な見直しを行うことで、つまらないミスをすることはありませんでした。
時間内に全問題の選択肢を読み終えることができないということは、厳しい言い方をすれば、まだまだ実力が足りていないのです。
ここで、2番目以降の選択肢を読み飛ばすという方法はどれくらい有効なのか、考えてみたいと思います。
過去問10年分を検証すると、選択肢1が正解である確率は約20%です。(個数・組み合わせ問題は除く)
続いて、ざっくりと、問題の説明文を読む時間を1、ひとつの選択肢を読む時間を1とすると、1問あたり5の時間を要することになります。
そのため、問題の説明文~選択肢1まで読み、それ以降は読まないようにすれば、3分の5=60%の時間を削減できることになります。
以上を考慮すると、全体で削減できるのは、わずか12%分(=20%×60%)の時間です。
たった12%の時間を減らすために、つまらないミスで簡単な問題を落としてしまうのは、あまりにも割りに合わない取引でしょう。
自信を持って選択肢1を選んだということは、かなり易しく感じる問題であり、そういった問題は他の受験生も確実に取ってきます。
合格のためには落とせない問題であり、全ての選択肢を読んで確実に正解しておく必要があるのです。
どうしても時短を図りたいのなら、知識の正確性を高めて読解スピードを12%高めるようにした方が、より安全に合格に近づけるでしょう。
⑧完璧主義の学習
私は、「まず一周してみる」という気持ちで、宅建試験の全範囲をやり通すようにしました。
もちろん、覚えていないと過去問が解けなくなるような知識はなるべく暗記するようにしていましたが、「忘れたらまたやればいい」という感覚で進めていきました。
まずは、暗記より理解を優先して、与えられたカリキュラムを一通りやり抜くことに専念しました。
その後、問題演習を繰り返していきましたが、その過程で分かったことは、「初学者の頃に身に付けた知識は意外と不正確」ということでした。
問題演習で初見の問題に触れたりして、新たな角度から光を当てることで、知識はより正確なものになっていくんですね。
加えて、宅建試験の各科目の論点には繋がっており、権利関係で民法の考え方が分かると、宅建業法も理解しやすくなったりもします。
そうだとすれば、初学者の頃に学んだことを、「まずは完璧な暗記だ!」と気合を入れて毎日反復して頭に叩き込んでいくようなことをすれば、不正確であったりムダな知識を詰め込むことになり、結果的に学習の効率性が下がることになります。
完璧主義に陥って先に進めないくらいなら、まずは一周してみることを強くオススメします。
⑨他の受験生の勉強法を鵜呑みにする
私は孤独な受験生時代を過ごしており、SNSで他の受験生と交流したりということはありませんでした。
それよりもフォローしていたのは、プロの講師や合格者の発信する情報です。
その結果、余計な情報に惑わされることがなく勉強を進めることが出来ました。
宅建試験は、受験生が10人いれば8人以上は不合格になる試験です。
SNS上では、オススメの勉強法を紹介している受験生もいますが、その受験生が合格するとは限りません。
いくらオススメとはいえ、合格という結果が出なければ、正しい勉強法とは言えないのです。
もちろん、他の受験生と励まし合うことは、辛い受験勉強を乗り越える上で大いにプラスになるでしょう。
しかしながら、他の受験生の発する情報を鵜呑みにし過ぎることは、とても危険なことなのです。
⑩結果の出ないやり方にこだわる
初学者の頃、「過去問の解説欄の余白に周辺知識を書き込む」という方法を自分でも試してみたことがあります。
過去問を1問解くたびに、該当する分野のテキストを参考にしながら、必要だと思われる周辺知識を過去問の解説欄に書き込もうとしていきました。
その結果、過去問1問の学習を進めるのに1時間以上の時間がかかってしまったのです。
初学者のうちは、どの周辺知識を書き込めばいいのか見当もつかず、1時間以上、過去問とテキストを見比べてウンウンと唸っているだけの状態だったんです。
こりゃダメだと思い、すぐにこの方法を辞めて、テキストをカスタマイズするやり方に変更した結果、学習もスムーズに進んでいきました。
宅建試験においては、自分で決めたことを最後までやりきることが大切なのですが、一方で、その都度軌道修正を図っていく柔軟性も大切なのです。
まとめ
この記事では、「宅建一発合格者がやらなかったこと」というテーマで、10の項目を紹介していきました。
私は、この10の項目の方法をやらなかったことで一発合格を果たすことができました。
しかしながら、この方法を行って合格した受験生がいることも事実です。
どうしても、勉強法には合う合わないがあるのです。
宅建の勉強法はネット上にも様々な意見が見受けられ、私の意見もその多様な意見の一部なのです。
学習を進めていると、多様な意見に振り回されそうにもなります。
大切なことは、人の意見をしっかりと見極める目を養ない、ゆるぎない自分軸で学習を進めることなのです。