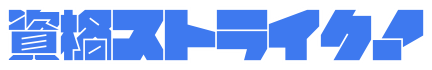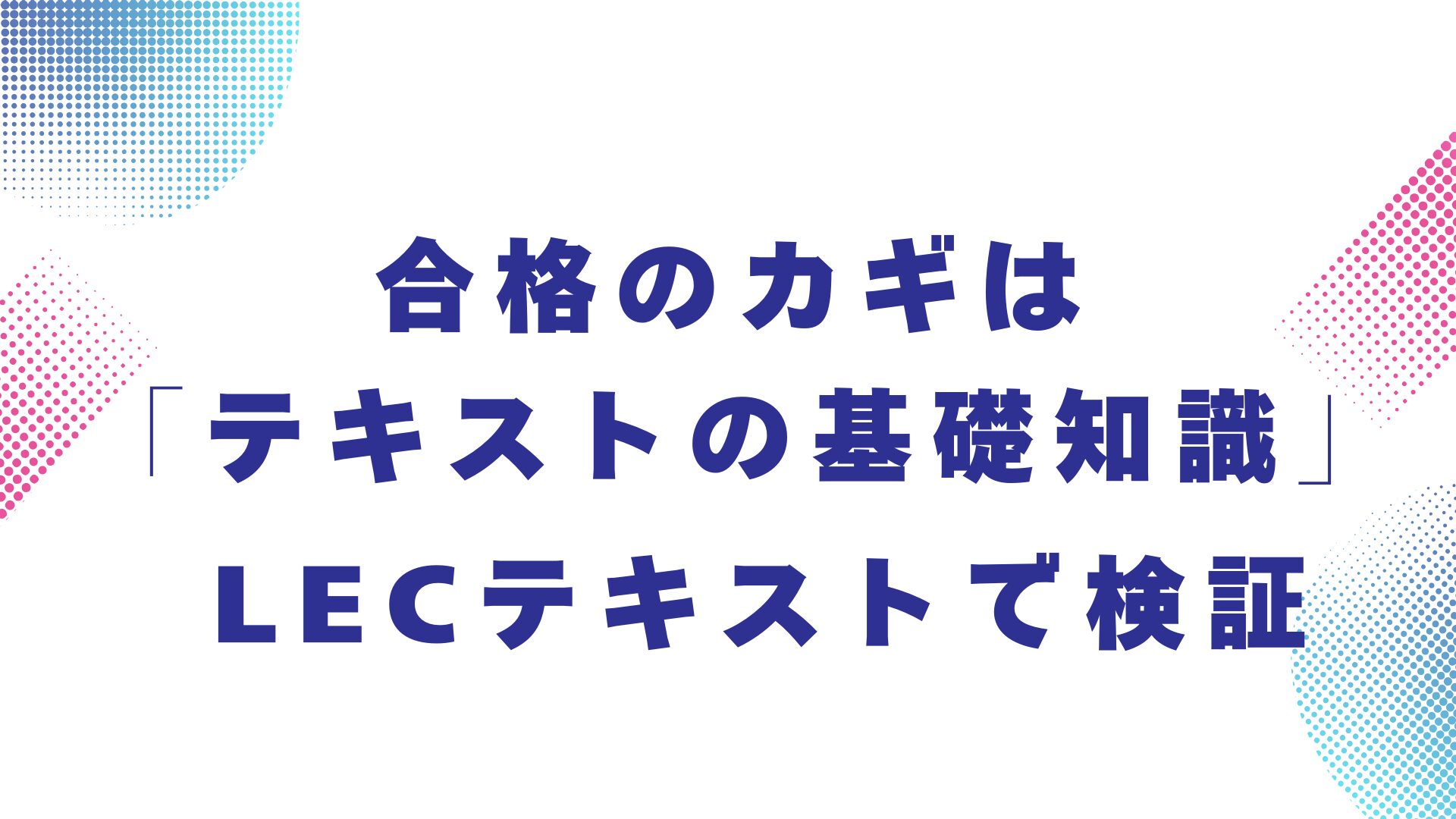どうも、私は当ブログの管理人、ぞねぞうと申します。
私は通信講座&独学&模試を解きまくるという、様々な方法を試しながら、R6年度宅建試験に44点で一発合格を果たすことができました。
そんな私が本試験を受けて分かったことは、タイトルの通り、テキストに書いてある基礎知識が宅建合格へのカギを握っていたということです。
本試験では、テキストに書いてある基礎知識を覚えていれば解ける問題が、35問も出題されていたのです。
そこでこの記事では、LECの出る順宅建士シリーズを参照しつつ、そのことを検証していきたいと思います。
(記事の最後には知識の参照元の一覧表も付けましたので、あわせてご確認ください。)
本試験では周辺知識が問われる?
最近の宅建試験においては、周辺知識という言葉がすっかり定着しています。
周辺知識とは、文字通り、一つの問題の周りにある知識のことです。
その問題で問われた知識に関係している知識のことであり、その問題では直接問われてはいないものの、同時に押さえておくべき知識のことです。
例えば、専任媒介契約の場合の業務処理状況の報告の頻度(2週間に1回以上)を聞いてくる問題を解いたら、それと同時に、専属専任媒介契約の場合の頻度(1週間に1回以上)も覚えておきましょう、ということなんですね。
宅建の本試験では、過去に出題された問題と全く同じ問題が出題されるということはまず考えられません。
それよりも、過去問の周辺知識を聞いてくる問題が数多く出題されるため、受験対策においては周辺知識を増やしていくことが欠かせないということなのです。
私も、受験生時代には周辺知識を増やそうと頑張っていましたが、今一つ腑に落ちないことがあり、あまり上手くいきませんでした。
周辺知識という言葉が漠然としていて、どこからどこまで覚えたらいいのか分からなかったのです。
「周辺知識があるなら、中心知識があるはず・・・。どの知識が中心知識なんだ?」と、若干混乱気味になっていました。
そのため私は、「テキスト&過去問の重要な知識を押さえ、それらをテキストに一元的に集約していく」という方法で学習を進め、そのまま本試験を迎えました。
そして本試験の現場で感じたことは、「テキストで見たことがある!」という知識が、相当な頻度で出てきたということです。
そう感じた私は、本試験の後に自宅に戻り、R6年度本試験の問題と、受験勉強を共に乗り越えてきたLECの「出る順宅建士」シリーズを照らし合わせてみました。
その結果分かったことは、本試験においては、「テキストレベルの基礎知識にアレンジを加えた問題」が大量に出題されていたということでした。
それでは次のトピックで、そのことを検証していきたいと思います。
「テキストの基礎知識」が合格へのカギ
テキストの知識から35問も出題されていた
私は、勉強した知識が最も残っている本試験当日の夜に、「これが分かっていれば正解の選択肢が選べる」という知識を、「出る順宅建士」シリーズの「合格テキスト」や「ウォーク問(過去問題集)」を参照しながらピックアップしていきました。
これらの知識は、「この知識を元にすれば、確実に1つの正解肢を選べる」、もしくは、「この知識を元にすれば、3つの誤答肢が判明し、消去法で正解が導ける」という基準により拾い上げたものです。
そして、その知識があれば解ける問題の数を、知識の参照元で分類してカウントしていきました。
その結果は、以下の通りです。
R6年度本試験 正解に必要な知識
| 参照元 | 問題数 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ Aランク | 24問 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ Bランク | 7問 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ以外(基礎) | 4問 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ以外(法改正) | 1問 |
| 出る順宅建士 ウォーク問 (正答率60%以上) | 3問 |
| 過去問題集 (ウォーク問以外) | 2問 |
| その他 (統計、土地・建物) | 3問 |
| 不明 | 6問 |
| 合計 | 50問 |
(参照元の一覧表はこちらです。)
なんと、「出る順宅建士 合格テキスト」に書いてある基礎的な知識を覚えているだけで、35問(24+7+4)も正解できるようになっていたのです。
これらの問題の構成比は、35問/50問と全体の70%を占めています。
R6年度本試験の合格最低点は37点なので、これらの知識だけでも最低点に大きく近づくことがわかります。
内容の補足説明
ここで、内容の補足説明をしていきます。
出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ
「出る順宅建士 合格テキスト」の合格ステップとは、合格に必要な知識が覚えやすいように整理されている、まとめ表のことです。
Aランクは最優先に覚えるべき知識をまとめてあり、Bランクはその次に重要な知識です。
実は、前のトピックで例に挙げた、媒介契約の業務処理状況の報告の頻度についての知識は、同じ合格ステップ(Aランク)の中にまとめて書かれており、それをそのまま覚えるだけでよかったのです。
周辺知識という言葉は、「知識クラスター」と呼んだ方がより分かりやすくなるかもしれません。
特に、Aランクの合格ステップに載っている知識は、周辺も中心もなく、全てをクラスター(集合体)として覚えるべき知識だからです。
出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ以外
続いて、「合格ステップ以外」のテキストの記述は、合格ステップのようなまとめ表にはなっていないものの、過去問で聞かれた知識を元に書かれている箇所です。
問題演習の際に、解答の根拠となる箇所をテキストから見つけ出し、そこにマーカーを引いておくと、重要な論点だけを効率よく拾い上げることができるのです。
実際に、自分の出る順宅建士テキストを見てみると、今回出題された基礎的な知識で解ける4問の正解の根拠となる箇所に、全てマーカーが引いてありました。
過去問や模試の基礎的な問題を解く際に、これらの正解の根拠をテキストに記録しておいたことで、本試験ではテキストが強力な暗記ツールになってくれたのです。
出る順宅建士 ウォーク問
その他に、「出る順宅建士 合格テキスト」には載っていないものの、「出る順宅建士 ウォーク問(正答率60%以上)」の知識が出所となっている問題が3問あります。
この問題を解く上で必要な知識は、ウォーク問に載っている正解率60%以上の基礎的な問題から得られる知識です。
テキストと過去問は平行して使いながら学習するものなので、これらの知識はテキストの基礎知識を覚える過程で一緒に身に付いていくでしょう。
必要ならば、テキストに書き足してもいいかもしれません。
その他(統計、土地・建物)
さらに、「その他(統計、土地・建物)」の問題が3問あります。
これらの問題は、テキストや過去問に載っていなくても、統計の問題は直前の対策で、土地・建物は受験テクニック(否定の意味(~でない)で断定している選択肢を見つける)で、いずれも何とかなる問題であったため、その他に分類しました。
もちろん、これらの問題も過去問演習が重要であることは言うまでもありません。
不明
「不明」となっている問題は、テキストや過去問にその問題を解くための知識が出てこないか、出てきたとしても正解するのが難しい難問です。
他の受験生も取れない問題であり、落としても合否に影響がないことから、「不明」と分類しました。
正解率60%以上の問題を確実に取るべし
検証の結果、出る順宅建士テキストに書いてある知識から35問が出題されていたことが分かりましたが、この中には正解率60%未満の問題も含まれています。
正解率60%未満の問題は、受験生によって正解・不正解が分かれてくる問題であり、本試験で確実に得点できるかは、正直微妙なところです。
例えば、R6年度の権利関係の問題では、問8が50.7%、問9が57.1%という割と高めの正答率だったのですが、難しいと感じた受験生も多く、LECでも難問と判定しています。
それだけ、正解率60%未満の問題を正解できるかどうかはアテにならないのです。
これらの問題を当て込んで合格最低点を上回る得点戦略は、とてもリスキーであると言えるでしょう。
逆に、正解率60%以上の問題を確実に得点していくことが合格への近道であるということが、以下の表からも分かります。
宅建試験 正解率ごとの問題数
| 正解率 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
| 80%以上 | 22問 | 23問 | 24問 |
| 70%以上 | 32問 | 32問 | 35問 |
| 60%以上 | 38問 | 38問 | 39問 |
| 50%以上 | 42問 | 44問 | 45問 |
| 40%以上 | 43問 | 46問 | 46問 |
| 最低点 | 36点 | 36点 | 37点 |
(正解率はLEC「出る順宅建士 ウォーク問 過去問題集(2023~2025年版)」の「受験者正解率」を参照)
いずれも、正解率60%以上の問題を正解するだけで、最低点を上回ることがよく分かります。
そこで、次のトピックでは、正解率60%以上という条件でフィルターをかけていきます。
正解率60%以上の問題でフィルターをかけてみると…
それでは、正解率60%以上の問題を正しく解答するために必要な知識を見ていきましょう
正解に必要な知識(正解率60%以上)
| 参照元 | 問題数 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ Aランク | 21問 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ Bランク | 6問 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ以外(基礎) | 4問 |
| 出る順宅建士 合格テキスト 合格ステップ以外(法改正) | 1問 |
| 出る順宅建士 ウォーク問 (正答率60%以上) | 3問 |
| 過去問題集 (ウォーク問以外) | 1問 |
| その他 (統計、土地・建物) | 3問 |
| 合計 | 39問 |
上記の表によると、「出る順宅建士 合格テキスト」に書いてある基礎知識を覚えておけば解ける問題が32問(21問+6問+4問)あり、構成比は79.5%(31問/39問)と高い比率を示しています。
その他に、「出る順宅建士 合格テキスト」には載っていないものの、「出る順宅建士 ウォーク問(正答率60%以上)」の知識が出所となっている問題が3問あります。
さらに、「その他(統計、土地・建物)」の問題が3問あります。
これらを加味すると、31問+3問+3問=37問であり、合格最低点37点に到達することになります。
結論:「テキストに書いてある基礎知識」が合格のカギを握っていた
これまで見てきたとおり、宅建試験では、正解率60%の問題を確実に取り切ることが重要であり、その中でも、「テキストに書いてある基礎知識」が大きな割合を占めていることが分かりました。
それらの基礎知識を正確に覚えておけば、後は+αの対策で十分に合格レベルに達していたのです。
以上から、宅建試験においては「テキストに書いてある基礎知識」が合格のカギを握っていると言えます。
では、なぜ宅建試験に落ちるのか
それでは、なぜ宅建試験では毎年8割以上の人が不合格となってしまうのでしょうか。
テキストに書いてある基礎知識だけでも十分に合格できる試験であるにも関わらずです。
それは、以下の2つの理由が考えられます。
理由①:そもそも基礎知識が身に付いていない。
受験生は、問題演習を進めていくことで様々な知識に触れていきますが、しばしばその情報の洪水に飲み込まれてしまうことがあります。
Aランクの知識をしっかりと固めればいいのに、Cランクの知識まで手を広げたりしていきます。
こうなると、頭の中の知識がとっ散らかってしまって、本来覚えるべき基礎知識が身に付かなくなってしまうのです。
これでは、本試験で出てくる初見の問題には知識の穴を突かれることになり、失点に繋がってしまいます。
まずは、テキストに書いてある基礎的な知識を、問題演習を通じてしっかりと身に付けていくことをいちばんに優先するべきでしょう。
理由②:現場思考の訓練が足りていない。
本試験の問題は、合格レベルに必要なものに限れば、テキストに書いてある基礎知識がベースになっています。
ただし、文章の表現を変えてみたり、紛らわしい選択肢を混ぜてみたりと、それらの基礎知識に様々なアレンジを加えた問題が出てくるのです。
そのアレンジのパターンは、それこそ無限大であり、全てを暗記することは不可能です。
過去問をひたすら周回し、正解の選択肢を何となく覚えるという勉強法では、本試験出てくるアレンジを加えた問題には対処できないでしょう。
そこで、テキストに書いてある知識をベースに、それらの知識を組み合わせて現場で問題を解いていくという、現場思考の訓練が必要なのです。
過去問を解く際に、正解・不正解の理由付けをしっかりと行うようにして、問題を解くプロセスを重視した学習を重ねていくことが、現場思考の力を鍛え上げてくれるでしょう。
まとめ
宅建試験は、他の難関国家資格の試験に比べれば、暗記すべき知識の量はそれほど多くはありません。
けっして知識量で殴り合う試験ではないので、1,000時間以上勉強して落ちる人もいれば、300時間以下の勉強時間で合格する人もいます。
毎年、短期合格者も一定数出ており、基礎知識さえ押さえておけば現場思考で何とかなる試験なのです。
その試験に合格するためは、テキストに書いてある知識をしっかり暗記すること、問題演習を通じて現場思考の訓練を重ねていくこと、この2つが欠かせません。
以上、長々と述べてきましたが、この記事が、宅建合格を目指す方の参考になれば何よりの幸せです。
2024年本試験 解答の参照元一覧
権利関係
| 番号 | 参照元 | ページ |
| 問1 | 合格テキスト 合格ステップ A | 43 |
| 問2 | 合格テキスト 合格ステップ以外(基礎) | 387 |
| 問3 | 合格テキスト 合格ステップ B | 274 |
| 問4 | 合格テキスト 合格ステップ A | 21 |
| 問5 | 不明 | |
| 問6 | 不明 | |
| 問7 | 不明 | |
| 問8 | 不明 | |
| 問9 | 不明 | |
| 問10 | 合格テキスト 合格ステップ A | 151 |
| 問11 | 合格テキスト 合格ステップ A | 355 |
| 問12 | 合格テキスト 合格ステップ B | 343 |
| 問13 | 合格テキスト 合格ステップ B | 286 |
| 問14 | 合格テキスト 合格ステップ A | 216 |
※「ページ」は、「2024年版 出る順宅建士 合格テキスト ①権利関係」、「2024年版 出る順宅建士 ウォーク問 過去問題集 ①権利関係」の該当ページです。
宅建業法
| 番号 | 参照元 | ページ |
| 問26 | 合格テキスト 合格ステップ以外 (基礎)、 過去問題集 (ウォーク問以外) | 170、 176、 H29-41-3 |
| 問27 | 合格テキスト 合格ステップ A | 104 |
| 問28 | 合格テキスト 合格ステップ B | 273、 275、 277 |
| 問29 | 合格テキスト 合格ステップ A | 31 |
| 問30 | 合格テキスト 合格ステップ A | 221 |
| 問31 | 合格テキスト 合格ステップ A | 287 |
| 問32 | 合格テキスト 合格ステップ A | 143 |
| 問33 | 合格テキスト 合格ステップ A | 154 |
| 問34 | 合格テキスト 合格ステップ A | 235 |
| 問35 | ウォーク問 (正答率60%以上) | 326 |
| 問36 | 合格テキスト 合格ステップ A | 111 |
| 問37 | 合格テキスト 合格ステップ以外 (基礎) | 175、 179、 186 |
| 問38 | 合格テキスト 合格ステップ以外 (基礎) | 288 |
| 問39 | 合格テキスト 合格ステップ以外 (基礎) | 63 |
| 問40 | 合格テキスト 合格ステップ A | 200 |
| 問41 | ウォーク問 (正答率60%以上) | 180、 188 |
| 問42 | 合格テキスト 合格ステップ A | 302 |
| 問43 | 合格テキスト 合格ステップ以外 (法改正) | 72、 92、 95 |
| 問44 | 合格テキスト 合格ステップ A | 200 |
| 問45 | 合格テキスト 合格ステップ A | 251 |
※「ページ」は、「2024年版 出る順宅建士 合格テキスト ②宅建業法」、「2024年版 出る順宅建士 ウォーク問 過去問題集 ②宅建業法」の該当ページです。
※過去問題集(ウォーク問以外)の場合、出題年度と問題番号を記載しています。
法令上の制限・税その他
| 番号 | 参照元 | ページ |
| 問15 | 合格テキスト 合格ステップ A | 53 |
| 問16 | 合格テキスト 合格ステップ A | 69 |
| 問17 | 合格テキスト 合格ステップ B | 188 |
| 問18 | 不明 | |
| 問19 | 合格テキスト 合格ステップ A | 268 |
| 問20 | 合格テキスト 合格ステップ B | 252 |
| 問21 | 過去問題集 (ウォーク問以外) | H26-21-1 |
| 問22 | 合格テキスト 合格ステップ A | 209 |
| 問23 | 合格テキスト 合格ステップ A | 332 |
| 問24 | 合格テキスト 合格ステップ A | 292 |
| 問25 | 合格テキスト 合格ステップ B | 387 |
| 問46 | ウォーク問 (正答率60%以上) | 328 |
| 問47 | 合格テキスト 合格ステップ A | 439 |
| 問48 | その他 (統計、土地・建物) | |
| 問49 | その他 (統計、土地・建物) | |
| 問50 | その他 (統計、土地・建物) |
※「ページ」は、「2024年版 出る順宅建士 合格テキスト ③法令上の制限・税その他」、「2024年版 出る順宅建士 ウォーク問 過去問題集 ③法令上の制限・税その他」の該当ページです。
※過去問題集(ウォーク問以外)の場合、出題年度と問題番号を記載しています。