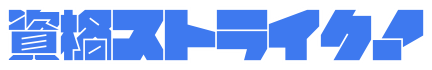こんにちは。私は当ブログの管理人、ぞねぞうと申します。
宅建試験において、「法令上の制限」という科目は、覚えなくてはいけない数値が多いので、とにかく暗記が大変です。
とくに、許可・届出・規制が必要な数値(面積・高さ)を覚える場合、一緒に「以上」「超える」という言葉も覚えなくてはいけないので、暗記に要する負担が増大するのです。
そこで、私が考えたゴロ合わせ、「異常なトシコさんの脳みそを食べる、超ヤバいケンタくん」を使ってみてください。
サイコパスでカオスなゴロ合わせですが、「法令上の制限」の暗記にかかる労力を劇的に減らすことができると思います。
それではこの記事で、このゴロ合わせについて解説していきます。
「異常なトシコさん」「超ヤバいケンタくん」とは?
「以上」「超える」の統一ルールに着目
「法令上の制限」という科目は、許可・届出・規制が必要な数値(面積・高さ)を覚える場合、一緒に「以上」「以下」「超える」「未満」という言葉も覚えなくてはいけないので、暗記にかかる労力がとても大きくなります。
そこで、「法令上の制限」で取り扱うそれぞれの法律に着目してみましょう。
実は、法律ごとに「以上」「超える」のルールが統一されているのです。
「以上」の場合に許可・届出が必要な法律:「都市計画法」「国土利用計画法」「農地法」
「超える」場合に規制・許可が必要な法律:「建築基準法(一部例外あり)」「宅地造成及び特定盛土規制法」
そこで、このゴロ合わせでまとめて覚えるのです。
異常(以上)なトシ(都市計画法)コ(国土利用計画法)さんの脳(農地法)みそを食べる、
超(超える)ヤバいケン(建築基準法)タく(宅地造成及び特定盛土規制法)ん
⇒異常なトシコさんの脳みそを食べる、超ヤバいケンタくん
サイコパスでカオスな光景を思い浮かべれば、覚えやすくなります。

このように、法律ごとの統一ルールを覚えておけば、許可・届出・規制が必要となる基準の数値(面積・高さ)を覚える場合でも、一緒に「以上」「以下」「超える」「未満」という言葉を覚える必要がありません。
基準の数値さえ覚えてけばいいので、暗記にかかる労力を大幅に省力化できるのです。
「以上」「以下」「超える」「未満」を整理しよう
「以上」「以下」「超える」「未満」
ゴロ合わせを使う前に、「以上」「以下」「超える」「未満」という表現の意味をしっかりと整理しておきましょう。
まず、「以上」「以下」の場合は、基準となる数値も含みます。
例えば、面積が「1,000㎡以下」という表現の場合は、1,000㎡ジャスト及び、999㎡、998㎡...という数値を含みます。
「1,000㎡以上」という表現の場合には、1,000㎡ジャスト及び、1,001㎡、1,002㎡...という数値を含みます。
続いて、「超える」「未満」の場合は、基準となる数値は含みません。
「1,000㎡未満」という表現の場合は、999㎡、998㎡、997㎡...という数値を含み、1,000㎡ジャストは含みません。
「1,000㎡を超える」という表現の場合には、1,001㎡、1,002㎡、1,003㎡...という数値を含み、こちらも1,000㎡ジャストは含みません。
宅建試験では、「以上」「以下」「超える」「未満」の意味をしっかり整理しておかないと、基準の数値にジャストの数値を聞いてくる問題で失点することになってしまいます。
言い換えテクニックで2種類に絞る
「法令上の制限」では、基準となる数値を覚えなければならないのと、その数値の後の「以上」「以下」「超える」「未満」の4種類の表現まで暗記しなければならないので、とっても大変です。
そこで、言い換えのテクニックを使って、「以上」「超える」の2種類に絞るのです。
その例として、「(面積)1,000㎡未満は許可が不要」という表現を考えてみましょう。
1,000㎡未満は許可が不要
| 面積 | 許可 |
| 998㎡ | 不要 |
| 999㎡ | 不要 |
| 1,000㎡ | 必要 |
| 1,001㎡ | 必要 |
| 1,002㎡ | 必要 |
「1,000㎡未満は許可が不要」という表現の場合、1,000㎡ジャストは含まないので、…998㎡、999㎡まで許可が不要となります。
その後の、1,000㎡ジャスト、1,001㎡、1,002㎡…からは許可が必要になります。
1,000㎡ジャストを含み、そこから上の面積は許可が必要になるということは、「1,000㎡以上は許可が必要」と表現することができます。
つまり、「1,000㎡未満は許可が不要」という表現は、「1,000㎡以上は許可が必要」と言い換えることができるのです。
この言い換えのテクニックを使えば、「○○以上の場合に許可・届出・規制が必要な法律」と「○○を超える場合に許可・届出・規制が必要な法律」の2種類のグループに大別することができます。
この2種類のグループは、冒頭で紹介したゴロで覚えられるので、暗記にかかる労力を劇的に減らすことができるのです。
「異常=以上」の場合に許可・届出が必要な法律
「都市計画法」
「都市計画法」では、「開発許可の例外」という論点がよく出題されます。
特に、規模の小さい開発行為を行う場合、面積によって許可の要否が変わってきます。
開発許可の例外
| 開発行為の種類 | 規模の小さい開発行為 |
| (1)市街化区域 | 1,000㎡未満は不要 |
| (2)市街化調整区域 | 許可が必要 |
| (3)区域区分が定められていない都市計画区域 | 3,000㎡未満は不要 |
| (4)準都市計画区域 | 3,000㎡未満は不要 |
| (5)都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内 | 1ha(10,000㎡)未満は不要 |
ここで、テキストなどでは「1,000㎡未満は許可が不要」という表現になっていますが、暗記の労力を減らすために、「1,000㎡以上は許可が必要」と言い換えて覚えるようにします。
都市計画法は、「以上」の場合に許可が必要、だから、「異常(以上)なトシ(都市計画法)コさん」と覚えるのです。
「国土利用計画法」
「国土利用計画法」では、「事後届出の面積要件」がよく出題されます。
事後届出の面積要件
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化区域以外の都市計画区域内 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡(1ha)以上 |
ここでは「以上」という表現になっているので、そのままゴロ合わせで覚えます。
国土利用計画法は、「以上」の場合に許可が必要、だから、「異常(以上)なトシコ(国土利用計画法)さん」と覚えます。
「農地法」
「農地法」の面積要件は数が少ないのですが、農地法4条が適用除外(許可不要)となる場合の農地の面積が問われる箇所があります。
| 農地法4条の適用除外(許可不要) | 農家が自己所有の農地(2アール未満のものに限る)を農作物の育成もしくは養畜のための農業用施設に供する場合 |
ここでも、「2アール以上は許可が必要」と言い換えて覚えます。
農地法は、「以上」の場合に許可が必要、だから、「異常(以上)なトシコさんの脳(農地法)みそを食べる」と覚えます。
「超ヤバイ=超える」場合に規制・許可が必要な法律
建築基準法
建築基準法では、定められた数値を「超える」場合に制限を受けるケースが多々あります。
例を挙げると、以下のようなものがあります。
- 建蔽率
- 容積率
- 日影規制
- 第一種・第二種低層住居専用地域等内の高さ制限
- 防火地域・準防火地域内における建築制限
- 建築物の構造
- 建築設備
- 建築確認
(数値はお手持ちのテキストでご確認ください。)
建築基準法は、「超える」場合に制限を受ける、だから、「超(超える)ヤバいケン(建築基準法)タくん」と覚えます。
但し、建築基準法には、数値は「~以上とする」という規制があるケースがあります。
そこで、その場合は例外として扱い、別のゴロ合わせで覚えることにします。
詳細は、後のトピックで説明します。
宅地造成及び特定盛土規制法
「宅地造成及び特定盛土規制法」では、宅地造成等工事規制区域において許可が必要となる盛土・切土の高さを問う問題がよく出題されます。
宅地造成等工事規制区域において許可が必要となる基準
| 宅地造成特定盛土等 | 許可が必要となる基準 |
| A崖を生ずる盛土 | 1m超 |
| B崖を生ずる切土 | 2m超 |
| C崖を生ずる盛土と切土 | 2m超 |
| D崖を生じない盛土 | 高さ2m超 |
| E面積 | 500㎡超 |
| 土石の堆積(一定期間経過後に除却するものに限る) | ①高さ2m超かつ面積300㎡超 ②面積500㎡超(①を除く) |
ここでも、「超える」場合に許可が必要となることがよく分かります。
宅地造成及び特定盛土規制法は、「超える」場合に許可が必要となる、だから、「超(超える)ヤバいケンタく(宅地造成及び特定盛土規制法)ん」と覚えます。
建築基準法の例外(「~以上」の規制がある場合)
前のトピックで述べた通り、建築基準法には、数値は「~以上とする」という規制があるケースがあります。
そこで、その場合は例外として扱い、別のゴロ合わせで覚えることにします。
「~以上」が出てくる項目は、以下の通り、「用途規制(劇場・映画館)」「換気」「道路規制」「階数」「採光」の5つです。
建築基準法の例外(「~以上」の規制)
用途規制(劇場・映画館)
用途規制を受ける建築物のうち、客席200㎡以上の劇場・映画館は、準住居地域に建設することができないという制限があります。
それ以外は、「○○㎡以内ならこの用途地域に建築OK」となっており、「超える」場合に制限を受ける表現になっています。
換気
換気に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対し20分の1以上にしなければならないという制限があります。
道路規制
建築物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法で定められた道路に2m以上接していなければならないという、摂動義務があります。
このように、道路規制の場合は、「以上」という表現を使用します。
階数
階数は、「2階以上」「3階以上」といったように、「~以上」の場合に制限を受けます。
採光
採光に有効な部分の面積は、住宅では、原則としてその居室の床面積に対し7分の1以上(一定の場合は10分の1以上)にしなければならないという制限があります。
ゴロ合わせ
そこで、建築基準法の例外である「用途規制(劇場・映画館)」「換気」「道路規制」「階数」「採光」の5つについても、ゴロを作りました。
異常(以上)者が、劇場(用途規制(劇場・映画館))で感(換気)動(道路規制)して、快(階数)哉(採光)を叫ぶ
⇒異常者が、劇場で感動して、快哉を叫ぶ
建築基準法の例外として、こちらも活用してみてください。
ゴロ合わせを使った問題の解き方
宅建試験の本試験では、基準の数値にピッタリの数値を聞いてくる、いやらしい問題が出てきます。
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で開発行為(規模は、1,000㎡であるものとする)を行う場合、開発許可を受けなければならない。解答:〇(2006年 問19-1)
ちょうど1,000㎡なので、許可が必要かどうか、一瞬迷うかもしれません。
そんな時には、問題で扱っている法律をしっかりと意識することです。
そうすれば、次のような思考プロセスを辿って正解に辿り着けるでしょう。
「この問題は、都市計画法の問題だな。」
「都市計画法…、そうだ、都市計画法だから異常(以上)なトシコさんだ。」
「1,000㎡以上ということは1,000㎡も含むから、この問題は〇だ!」
こんな感じで、頭の中にゴロ合わせを思い浮かべて問題を解くようにしてください。
私も、このテクニックを使って暗記を省力化することに成功しました。
まとめ
この記事では、「法令上の制限」の暗記を省力化するゴロ合わせを解説していきました。
宅建試験においては、知識の精度が求められます。
この記事のゴロ合わせのように、暗記する事項を絞り込んで何度も反復した方が、正確な知識が身に付くのです。
何でもかんでもゴリゴリと暗記するより、もっと暗記の量を減らせないか、そういったことを意識して学習を進めていきましょう。