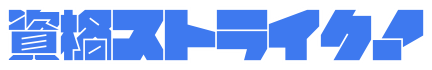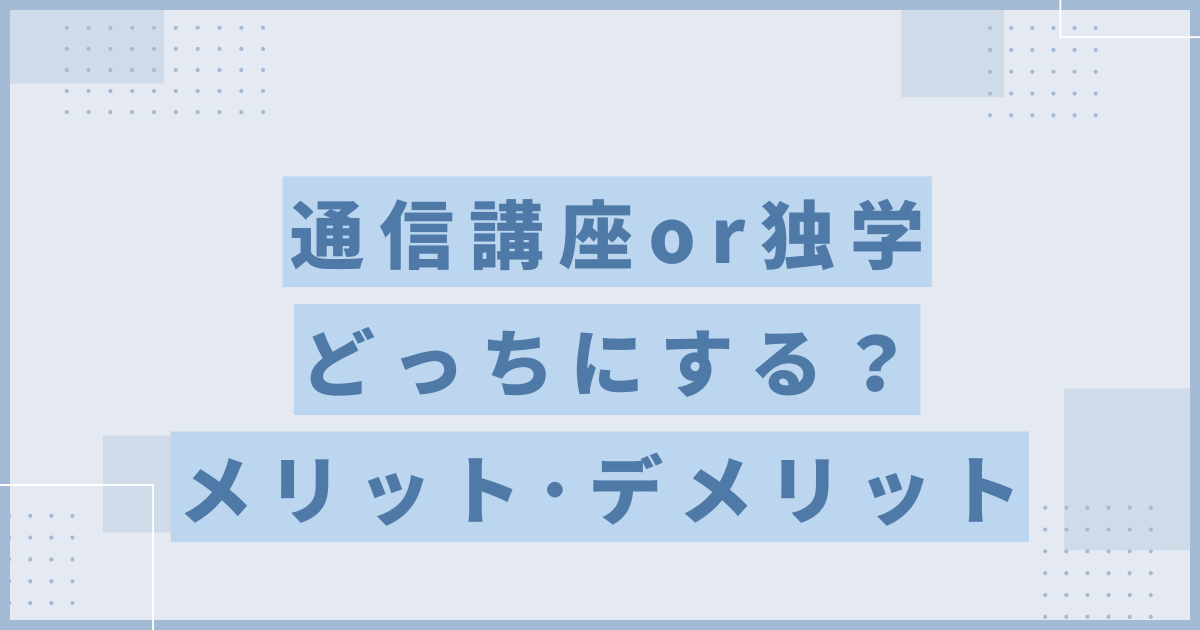こんにちは。私は当ブログの管理人、ぞねぞうと申します。
私は2024年度の宅建試験に挑戦し、実質3ヵ月20日の学習期間を経た後、本試験では44点の成績で一発合格を果たすことができました。
その私が行っていたのが、資格スクール(クレアール)の通信講座と、それに加えて新しい過去問題集(LECのウォーク問シリーズ)を自分で学習するという、通信講座と独学のハイブリッド型の勉強法です。
こうした勉強を進める過程において、通信講座と独学のそれぞれのメリット・デメリットが見えてきました。
そこでこの記事では、通信講座と独学のどちらにすべきか悩んでいる方に向けて、その両方を経験した私の視点からアドバイスができればと思っています。
これから宅建試験の受験を検討している方は、是非とも参考にしてみてください。
通信講座のメリット
カリキュラムに沿って効率よく学習できる
宅建試験の出題範囲は膨大なものであり、出題頻度の高い知識とそうでない知識をしっかりと見極め、メリハリをつけた学習を行っていくことが求められます。
この点に関して、資格スクールは長年培われた受験ノウハウを元にカリキュラムを練り上げており、そのカリキュラムに従っていくことで、出題頻度の高い知識を中心に効率よく学習することができるようになっています。
独学の場合だと、出題頻度の高い知識が今一つ分からず、ついつい余計な知識まで覚えようとして、気が付けば膨大な時間を費やしていたということも起こり得るでしょう。
そうなれば、通信講座を受講していた方がよっぽど時間の節約になったはずです。
学習スケジュールを立てるのが容易である
独学の場合、テキストを読んでも分からない時にはYouTube動画を参考にするというケースが多くなります。
YouTube動画のクオリティにはバラつきがあり、基本的には個別の質問は出来ず、どうしても理解できない場合は、さらに別の動画を見る必要が生じるかもしれません。
その場合、一つの単元の理解にどれだけ時間がかかるのか見当がつかず、学習の総量が把握できないため、本試験までの全体的な学習スケジュールを立てることが難しくなります。
通信講座であれば一定の質は確保されており、分からない時には質問をすることができるので、一つの単元の消化にかかる時間は割と安定していると言えます。
講義の回数と全体の講義時間も最初から分かっているので、学習の総量も可視化され、学習スケジュールも立てやすくなります。
本試験までにどの程度の時間的な余裕があるのか、余裕があると分かれば問題演習をさらに追加するということもできるでしょう。
個別に質問ができる
テキストを読み込んで、過去問も解けるようになってくると、自分の知識は完璧だと思うようになってきます。
それでも、別の問題を解いてみると、意外とボロが出たりして、自分の知識はまだまだ不正確だと気付かされることがあるのです。
こうした知識をより正確なものにするために、質問をするという手段はとても有効です。
通信講座の場合、無制限やチケット制などの違いはありますが、受講生の質問にはしっかりと答えるというサポート体制が整っていることがほとんどです。
質問によって疑問点を解消することは、知識の正確性を高めるとともに、記憶にも残りやすくなって知識の定着にも役立ちます。
法改正など、最新の情報が得られる
市販のテキスト・過去問題集は、本試験の前年の10~12月には既に発売されており、直前予想模試でも本試験のある年の5~6月頃には発売されています。
それ以降の時期でも、通信講座であれば最新の傾向を踏まえた直前対策講義を受けることができるため、法改正にも対応がしやすくなるでしょう。
この点について、独学の場合は別の方法を考える必要があります。
通信講座のデメリット
一定の費用がかかる
通信講座は安くても大体2万円台から、カリキュラムやサポート体制が充実している講座の場合だと、10万円~20万円という価格となることも珍しくはありません。
どうしても費用を抑えたいという人には、独学の方が向いているでしょう。
講義動画の視聴に一定の時間がかかる
海外の研究では、読むインプットの速さは、聞くインプットよりも2倍速いことが明らかになっています。
通信講座の講義動画の視聴は典型的な聞くインプットであり、読むだけでテキストをスムーズに理解できるという前提ならば、独学の方がスピードは速いのです。
実際に、私の場合は、クレアールの基本講義視聴+過去問2周に180時間を費やしましたが、LECのウォーク問テキスト読み込み+過去問2周には120時間しかかかりませんでした。
クレアールの過去問の問題数は336問であったのに対し、LECのウォーク問の問題数は500問と約1.5倍も多かったのにも関わらずです。
以上のことから、本試験までに残された時間を考え、その時間に見合った通信講座を選ぶことが大切だと言えます。
講義動画を視聴するだけで勉強した気になってしまう
通信講座の講義は、どの資格スクールも力を入れて作り上げており、講義動画はとても分かりやすく出来ています。
難しい概念も噛み砕いて説明してくれるため、様々な知識への理解が深まり、いかにも「自分は勉強しているんだ」という気持ちにさせてくれます。
講義を見終わった時には、「ここまでやり切った」という達成感も得られることでしょう。
しかしながら、ここで復習や過去問演習をおろそかにすれば、本当の実力は身に付きません。
講義が充実している分、ついつい油断をしてしまうというのも、通信講座のデメリットと言えるかもしれません。
カリキュラムが合わない場合でも変更はできない
学習を進めていくうちに、通信講座のカリキュラムが「自分には合わない」と感じることもあるでしょう。
そう感じたとしても、既に受講を始めた以上、最後までやり切るしかなくなります。
講師や教材が合わないと思ったとしても、抜本的な変更は難しいでしょう。
どうしても変更したいのなら、他社の通信講座でやり直すしかなく、それまでにかけた時間と費用がムダになってしまいます。
通信講座は学習内容がパッケージ化されている分、柔軟に方針を変更するのが難しいのです。
独学のメリット
費用が安い
例えば、2025年版の「出る順宅建士 ウォーク問」シリーズを6冊全て(テキスト3冊+過去問3冊)買い揃えたとしても、総額は13,970円です。
ここに問題集や模試を多少追加したしても、20,000円以下の費用に収まるでしょう。
費用の安さという観点では、独学の方が優っているのです。
勉強方法を自分流にカスタマイズできる
通信講座の場合、途中でカリキュラムを変更することは難しく、「どうしても変えたい」という場合は他社の通信講座でやり直すことになってしまいます。
独学ならば、今使っている教材がどうしても合わなければ、他社の教材を買い直すことができます。
学習の参考にしているYouTube動画が分かりにくいと思ったら、他のYouTube動画に変えればよく、当たり前ですがその場合でもお金はかかりません。
自分のやりたいようにやれるというのが、独学の強みなのです。
上手くいけば通信講座よりも短い期間で学べる
テキストを読むだけでスムーズに学習内容を理解できることが前提になりますが、独学は通信講座より短い期間で学べる可能性があります。
通信講座のデメリットでも述べた通り、読むインプットの速度は、聞くインプットよりも2倍速くなっています。
テキストの文章を読んだだけで、宅建試験の各分野の基礎知識を正確に理解できるのならば、通信講座よりも遥かに速いスピードで学習を進めることができるのです。
独学のデメリット
モチベーションを保つのが難しい
通信講座はあらかじめカリキュラムが決まっており、学習スケジュールを立てることが容易になっていて、学習の進度も分かりやすく、本試験まで気持ちを切らさずに続けやすくなっています。
申し込む際に一定の費用がかかっているため、「払ったお金をムダにはできない!」という気持ちも学習を続ける上でのモチベーションになるでしょう。
一方、独学の場合、カリキュラムも学習スケジュールも、自分で自由に決められます。
自由すぎて「何をどうすればよいか分からない…」という心の迷いから、勉強法ジプシーに陥り、学習のモチベーションも段々と低下してしまうということもあり得るのではないでしょうか。
個別に質問が出来ない
通信講座の場合は、講義や教材でよく理解できない箇所があれば、個別に質問をすることができます。
しかしながら、独学の場合、テキストや過去問の解説を読み込んだり、YouTube動画を見たりして、それでも理解出来ないことがあったとしても、質問をすることが出来ません。
YouTube動画のコメント欄で質問するという方法もありますが、全ての質問に答えてもらうことは難しく、基本的には自力で解決することになるでしょう。
どうしても疑問を解消したいという場合には、通信講座の方が有利なのです。
理解が進まない場合、通信講座よりも時間がかかる
通信講座は、講義動画の視聴に一定の時間がかかりますが、内容を理解できない場合に質問により解決することができるため、学習にかかる時間が読みやすいというメリットがあります。
独学の場合は、基本的に質問ができないため、テキスト・過去問の解説を読んでも理解できない場合は、YouTube動画を参照することになります。
それでも疑問を解消できない場合は、また別のYouTube動画を参照することになり、そうしたことを続けていれば、通信講座を受講するよりも遥かに長い時間がかかってしまうでしょう。
独学が通信講座よりも速く学習できるというのは、テキストを読むだけで学習内容をスムーズに理解できるという前提条件が必要であり、そのことは受験生によってかなり個人差があるのが現実ではないでしょうか。
情報戦では不利になる
宅建のテキスト・過去問題集は、本試験の前年には既に発売されており、直前予想模試でも本試験のある年の5~6月頃には発売されています。
しかしながら、その後にも法改正等を踏まえて出題傾向が変わってくる可能性があります。
通信講座であればその点もフォローを受けることができますが、独学の場合は自分で情報収集しなければならず、不利であることは否めないでしょう。
通信講座はこんな人におすすめ
それでは、通信講座はどのような人におすすめなのでしょうか。
以下に当てはまる人には、通信講座の方が向いていると言えます。
宅建の初学者
初学者の頃は、重要な知識とそうでない知識の判別がつかず、ついつい余計なことまで覚えようとしてしまうことがあります。
そのため、「覚える知識が多すぎる!」と感じ、最悪の場合は勉強を挫折することになるかもしれません。
そうならないように、通信講座では覚えるべき知識を絞り込んでくれるので、初学者もムリなく学習を続けることができます。
勉強が苦手な人
勉強が苦手な人は、そもそも何をどのように勉強したらいいのかが分かりません。
この点に関しても、通信講座では、本試験までの学習の流れ、科目別の学習の仕方、復習のタイミング、問題の解き方などなどを、詳しく教えてくれます。
こうしたカリキュラムに従っていくだけで、勉強が苦手な人でも合格レベルに必要な実力を身に付けることができるのです。
独学はこんな人におすすめ
以下に当てはまれば、独学を選んでもスムーズに学習を進められるでしょう。
自己管理ができる人
本試験までにやるべきことを明確化し、自分のモチベーションを維持できる人は、独学でも結果を残せるでしょう。
宅建試験においては、テキストの基礎知識を覚えることと、過去問演習の徹底が合否のカギを握っています。
何も特別な教材が必要なわけではなく、市販の教材を活用してしっかりとやり切ることができれば、独学でも十分に戦えるのです。
情報分析力の高い人
宅建試験においては、書籍やYouTube動画など、様々な情報が溢れています。
そうした大量の情報の中から質の高い情報だけを見つけ出す能力が高い人は、自分にとって最適な勉強法を作り出すことができます。
通信講座のカリキュラムにも負けない、オリジナルのカリキュラムに従うことで、本試験でも戦える十分な実力を身に付けることができるでしょう。
まとめ
この記事では、通信講座と独学のどちらにすべきか悩んでいる方に向けて、その両方を経験した私の視点から考えたことをまとめてみました。
これから宅建試験の受験を検討している方の参考になれば幸いです。
通信講座も独学も、それぞれのメリット・デメリットがあります。
そのどちらを選ぶのか、大切なことは、自分が選んだ方を正解だと信じ、最後までやり切ることだと思います。