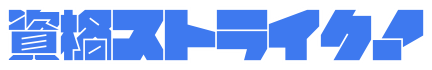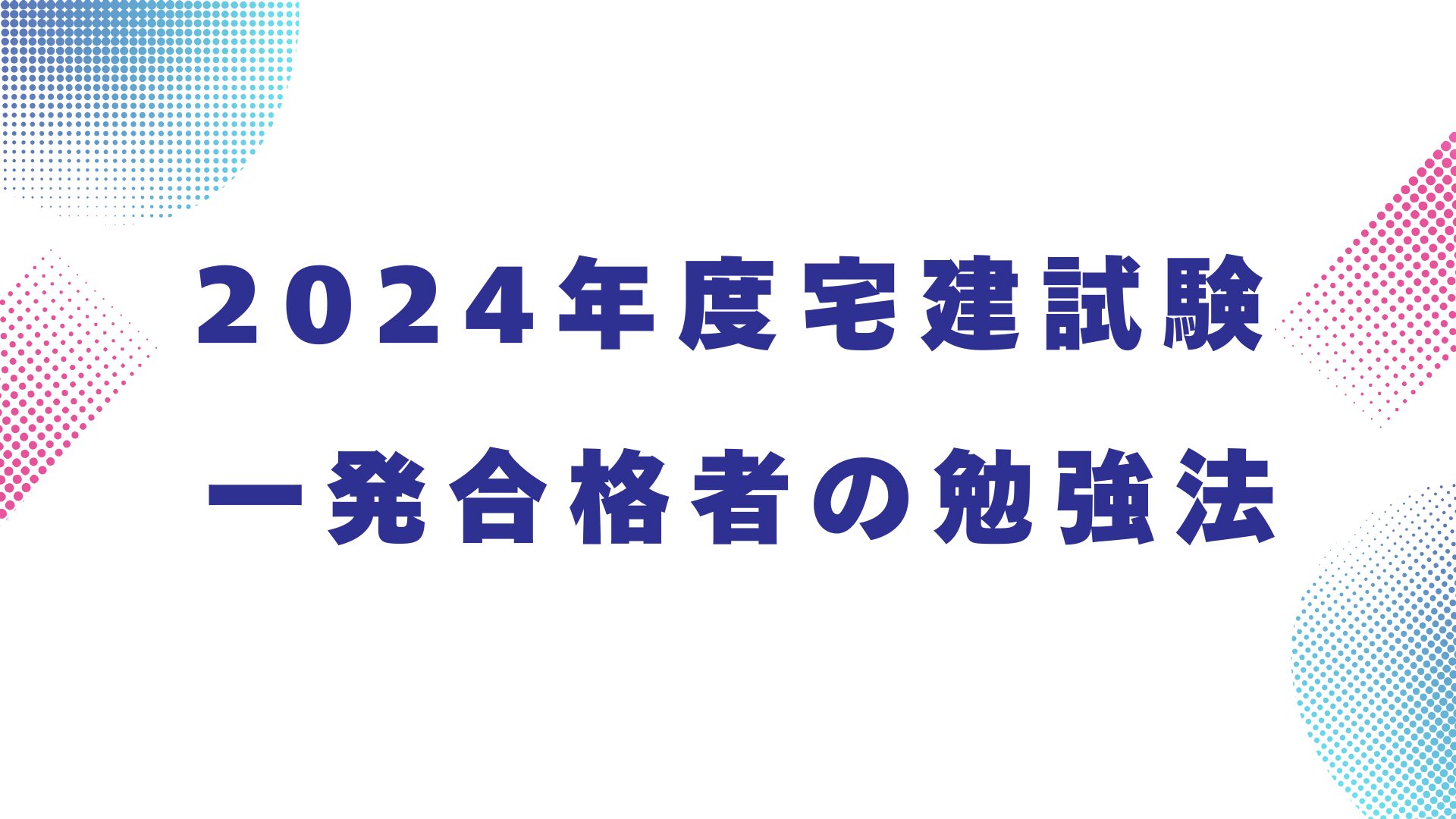どうも、私は当ブログの管理人、ぞねぞうです。
私は、2024年度の宅建試験に挑戦し、資格スクールや独学など様々な勉強方法を試しながら、本試験では44点で一発合格を果たすことができました。
私の挑戦の道のりは、こちらの合格体験記にまとめています。
合格体験記を書きながら、勉強法についてはまだまだ書き足りないと感じたので、この記事ではそれらにフォーカスしていきたいと思います。
私の受験期間は4か月間(コロナ休養のため実質3ヵ月と20日)であり、その期間に行った勉強法を順を追って説明していきます。
また、良かった点や反省点についても併せて記しておきました。
これから宅建試験の受験を検討している方は、是非とも参考にしてみてください。
通信講座の受講(本試験4カ月前~2カ月前)
クレアールの「パラレル学習法」
まず私は、通信講座の受講から宅建試験の学習を始めました。
受講したのは、クレアールの「2024・25年合格目標 完全合格セーフティコース」という通信講座です。
講座の大きな特徴は、「パラレル学習法」という勉強法であり、これは、各分野の一つの単元の基本講義を終わらせてから、直後にその単元の過去問の演習を行い、講義内容の定着を図るというものです。
テキストをなるべく細かいユニットに区切り、基本講義による基礎知識の理解と、問題演習による基礎知識の定着というサイクルを、パラレル(平行)に進めていくというイメージですね。
例えば、宅建業法であれば、免許制度の講義動画を一通り視聴してから、続けて免許制度の過去問を解くといった流れになっています。
実際に私もパラレル学習法に則り、一つの単元の基本講義を受講した後、その単元の過去問の演習を行い、基礎知識の定着を図っていきました。
また、基本講義を受講した直後に過去問を解くことを1周目の周回としてカウントし、およそ3日以内に再び同じ問題を解くことを2周目の周回としてカウントしていました。
このように、1周目と2周目の周回をほぼ同時に進めることで、復習を効率化し、記憶の定着を図っていきました。
プロセスを重視した過去問演習
宅建試験の学習で最もやってはいけないことは、問題文と解答を丸暗記するということです。
こうなると、本試験で過去問と形を変えた問題が出題された場合に対処ができなくなってしまいます。
そこで私は、次のように、解答のプロセスを重視した過去問演習を行っていました。
まず、4択式の過去問題集(クレアールの過去問題集は分野別の4択式)でも、一問一答形式のつもりで、それぞれの選択肢の正誤判定を行っていきます。
次に、一つ一つの選択肢について、問題文の中から解答に必要なキーワードを見つけ出し、キーワードから正誤を判定して解答を導き出すようにしていきました。
キーワードを見つけるために、問題文の場面設定(誰が、どこで、何をしたetc)にも着目するようにしていました。
また、過去問を解き終わった後は、必ずテキストに戻り、解答の根拠となった個所を確認するようにしていました。
このように、過去問とテキストを行ったり来たりすることで、問題文のキーワード抽出や正誤判定に必要な知識が身に付き、問題を解くプロセスが段々と分かってきました。
テキストをカスタマイズ
過去問演習の1周目では、問題を解いた後に必ずテキストに戻り、解答の根拠となった個所にマーカーを引くようにしていきました。(良かった点①)
また、他の問題を解いても、解答の根拠は同じだったりすることがあるため、その場合も赤線を付け足すなどして再び参照したことが分かるようにしました。
こうすれば、後でテキストを見返す際に、マークで強調した個所を中心に見返すことで、短時間で効率的な復習ができるようになります。
過去問のフィルターを通してテキストの情報を絞り込んだことで、覚えるべき個所が明確になっていくからです。
また、2週目と3周目は、間違えた個所や曖昧だった個所に絞ってマーカーを引き、1周目と同じ箇所を間違えた場合には赤線を付け足すなどして、前回も間違えていることを強調するようにしていました。
このようにマーキングの厚塗りをしておけば、演習を重ねるごとに自分の弱点が分かるようになってきます。
さらに、過去問にはよく出題されるものの、テキストに記載が無い知識は、その都度テキストに書き足すようにしてきました。
以上のように、マーキングによる絞り込みや強調、書き足しによる情報の追加により、テキストは自分に最も適した教材へと進化していくのです。
この方法は、どんな受験生にも幅広く対応できる再現性の高いものとなっています。
ベースとなっているのは受験のプロが作成したテキストであり、そこにカスタマイズを加える程度なら、受験生の個人の能力差はあまり関係が無いからです。
分野別の勉強法
このトピックでは、分野別の勉強法について述べていきたいと思います。
クレアールの通信講座のカリキュラムは、①宅建業法→②権利関係→③法令上の制限・税その他、という順番になっています。
私もこのカリキュラムに従い、宅建業法から学習を始めました。
宅建業法
権利関係に比べると学習の範囲は狭いのですが、学習の密度は高く、全範囲から満遍なく出題されており、宅建試験において最も重視すべき分野と言えます。
クレアールでも宅建業法は重視しており、理解を中心に据えた講義で知識の定着が図れるようになっています。
私も、基本講義を集中して聞き、講師が板書した図解をテキストの余白に書き加えたりして、宅建業法をしっかりと理解しようと心掛けました。
(ただここで、基本講義を受けている際に、テキストの中で重要だと感じた個所に所構わずマーカーを引いたため、復習を行う際に読みにくくなってしまいました。(反省点①))
また、講師の雑談もしっかり聞くようにしており、雑談の内容からイメージと結びつけて理解をするようにしていました。
それでも、宅建業法は、理解に加えて暗記が必要な分野であり、特に、35条・37条書面絡みの問題は、暗記する個所のあまりの多さに驚かされました。
対策として、講義で教わったゴロを、お風呂やトイレでも暗唱するなどしてインプットするとともに、過去問を解く際にはゴロを頭の中で唱えながら答えを導き出すようにしてアウトプットしていきました。
このように、インプットとアウトプットを交互に繰り返すことで、基礎知識の定着を図っていきました。
権利関係
権利関係は、法律の考え方をしっかりと理解していないと得点することが難しく、初学者には多少とっつきにくい分野となっています。
さらに、内容の難しさに加え、出題範囲がかなり広く、その中から年度によって出たり出なかったりという出題傾向にあり、難易度もかなりバラツキがあります。
それら2つの難点への対策としては、まず、法律の概念を難しい言葉でそのまま考えるのではなく、簡単な言葉に置き換えて考えるということです。
私も、クレアールの講師の解説を参考にしつつ、法律の仕組みをなるべく分かりやすい言葉に置き換えて理解するようにしていました。
また、事例問題を解くのに欠かせない、関係図を書く方法も、講師の板書を参考にしながら学んでいきました。
続けて、出題範囲の広さへの対策としては、一言で言うと「手を広げ過ぎない」ということにつきます。
民法には1,000条を超える条文があり、それら全てを暗記することは非常に困難であります。
いわば周辺知識だらけの分野であり、過去問の周辺知識を拾っていこうとしたら、勉強がドツボにはまってしまいます。
そこで私は、基本講義および過去問演習の内容をマスターすることに注力し、それ以外の余計な知識は覚えないようにしていました。
また、講義中に出題頻度をA~Cでランク付けしてくれるため、そのランク付けに沿ってメリハリをつけた学習を行い、捨てるところはバッサリと捨てていました。
さらに、特別法(借地借家法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法)は権利関係の中でも数少ない暗記モノの単元であり、この単元に関しては宅建業法と同じようにゴロ合わせを駆使して暗記を進めていきました。
このやり方でも、本試験において権利関係の基礎的な問題を解く際には、特に支障はありませんでした。
法令上の制限・税その他
法令上の制限及び税その他は、良くも悪くも暗記重視の分野と言えます。
問題文も宅建業法や権利関係と比べると短く、知識があれば解ける問題も多いため、ここで失点するのは実に勿体無いのです。
権利関係ほど内容は難しくはなく、問題文も長くはないため、あまり深くは考えず、ゴロ合わせも駆使してサクサクと暗記を進めるようにしていました。
また、許可が必要な面積を問われる問題で、「○○㎡以上」と「○○㎡を超える」の2つのケースがあり、それぞれを覚えておく必要があるため、テキストに戻って全体像を把握し、なるべくまとめて暗記すること効率化を図っていました。
通信講座の受講に要した期間
受講を開始したのが2024年の6月23日であり、基本講義+過去問解説講義を全て視聴し、それに対応する過去問の3周目の周回を終えたのが8月23日であったことから、およそ2か月かけてカリキュラムを消化したことになります。
これらの学習に要した時間は、基本講義+過去問解説講義の視聴及び過去問の2周の周回の合計が180時間、3周目の過去問の周回が約40時間であり、それらを合わせると合計で約220時間となっています。
過去問題集の独学(本試験2カ月前~1カ月前)
LECの「出る順宅建士」シリーズ
クレアールの講義が一段落した後は、LECの「出る順宅建士 」シリーズの学習を開始しました。
LECの「出る順宅建士 ウォーク問 過去問題集」も、各分野合わせて550問(50問は2023年度本試験問題)というボリュームを誇っており、基礎を一通り身に付けた後に、問題演習のパターンを増やす目的で使用しました。
ここでは、テキストと過去問題集の解説を読み込んで理解を進めていくという、独学型の方法論を取り入れました。
クレアールの講義を受けて基礎は身に付いていたため、力試しとしてまず最初に過去問を解くようにしました。
一つの過去問を解いた後は、テキストに戻って解答の根拠となる知識を確認していきます。
ここでも、クレアールのテキストを使用していた時と同じ基準で、複数回にわたって参照した個所は、その都度マークを塗り重ねて重要であることが分かるようにしていました。
また、LECのテキストには余白に十分なスペースがあり、情報を書き加える等のカスタマイズがやりやすかったため、「過去問にはよく出てくるけど、テキストには記載の無い知識」を、適宜書き足すようにしていました。
このようにすることで、テキストの中から重要な情報が浮かび上がり、基礎知識の更なる強化へと繋がっていきました。
さらに、解答の根拠となる知識だけでなく、その知識に関連する知識も確認するようにしていました。
特に、ウォーク問は各トピックの最後に「合格ステップ」というまとめ表があり、情報がよく整理されてまとめられています。
この合格ステップも活用し、知識を点で捉えるのではなく、なるべく全体的な視点で把握するように努めていました。
合格ステップの精度はとても高く、この内容をしっかり覚えたことで、本試験では合格率60%以上の問題39問の全問正解という結果に繋がりました。
分野別の勉強法
宅建業法
学習方法は通信講座で過去問を解いていた時と基本的には同じで、問題を解くプロセスを重視し、ゴロ合わせを頭の中で唱えながら問題を解くようにしていました。
クレアールの講義で教わったゴロ合わせも有効だったので、それらも組み合わせていきました。
権利関係
権利関係も、通信講座と同様の学習法であり、余計な周辺知識に手を広げることはしませんでした。
過去問とテキストを往復しながら、まずは過去問を解く上で必要な知識を優先して覚えるようにしていました。
法令上の制限・税その他
法令上の制限・税その他も、通信講座と同様の学習法です。
LECの用途規制の表は覚えやすかったため、この表を拡大コピーしてゴロを書き込み、常に持ち歩いて暗記するようにしていました。
その他の問題集
ウォーク問シリーズの過去問を周回しながら、同じLECの「出る順宅建士 一問一答○×1000肢問題集」を使用し、基礎知識の抜け漏れがないかを確認するようにしていました。
一問一答形式であれば、また違った角度から基礎知識のチェックができるので、ここでも知識の正確性が高まりました。
過去問題集の独学の効果
クレアール過去問の3周分周回に加え、LECウォーク問の2周分の周回を終わらせたところ、しっかりとした基礎知識が身に付いた手ごたえを感じていました。
このタイミングで、初めての模試ということで、クレアールの全国公開模試を受けたところ、いきなり44点をマークすることができました。
過去問とテキストの往復を繰り返し、ミルフィーユのように知識を塗り重ねたことで、知識の正確性が高まり、初見の問題への対応力も強化されていたのです。
過去問題集の独学に要した期間
LECのウォーク問の2周分の周回に約120時間、一問一答問題集の1周分の周回に約10時間を費やし、1か月の学習期間を要することになりました。
学習時間の累計は、クレアール通信講座+過去問3週の約220時間と合わせて、この時点(9/21)では約350時間となっていました。
直前期の勉強法(本試験1カ月前~当日)
年度別の過去問題集
基礎知識を身に付けるのは分野別過去問題集が最適です。
ただし、分野別過去問題集は、本試験慣れが出来ず初見の問題への不安が残るというデメリットもあります。
同じ単元の問題が立て続けに並んでいるので、問題を解いていくうちにパターンを覚えてしまい、次の問題の正解がなんとなく分かってくるのです。
本試験では問題がランダムに並んでおりこの通りには行かないため、別途、慣れを作っておく必要があります。
そこで私は、LECの「出る順宅建士 過去30年良問厳選模試」と、TACの「わかって合格(うか)る宅建士 過去問12年PLUS(プラス)」を活用し、本試験への慣れを作るようにしていました。
これらは、本試験と同じように50問の問題が並んでいる年度別の過去問題集です。
時間を計って解くことで、本試験のシミュレーションをするようにしていました。
また出題頻度の低い知識には深入りしないようにして、基礎知識の確認と初見の問題を解くための現場思考の訓練だと割り切って使いました。(良かった点②)
「出る順宅建士 過去30年良問厳選模試」は、6回分を1周だけ周回し、「わかって合格(うか)る宅建士 過去問12年PLUS(プラス)」は7回分を1周だけ周回しました。
模擬試験の活用
初見の問題への対応力をさらに高めるため、模擬試験も活用しました。
自分で採点を行う、いわゆる自力模試として、LECの「出る順宅建士 当たる!直前予想模試」を4回分、日建学院の「これで合格!宅建士直前予想模試」を2回分、それぞれ1周だけ解きました。
さらに、会場で受験するタイプの模試として、TACの「令和6年度全国公開模試」を受験しました。
これは、本試験と同じ13時~15時の時間帯の試験を受験し、騒音環境に慣れたり、お腹の調子などの体調を見極めたりと、本番の予行演習として活用しました。
模擬試験の問題も、基礎知識の確認と現場思考の訓練として割り切り、模擬試験で問われたマニアックな知識(特に権利関係)については無視することにしました。
直前期に暗記中心の学習
私の学習プランは、前半戦は暗記よりも理解を重視して学習を進めるというものでした。
暗記のスケジュール表を作り、それに基づいて復習のペースを徹底管理するといった方法も取り入れませんでした。
宅建試験では、すぐに覚えられる知識と何度も反復しないと覚えられない知識が混在しており、スケジュール通りには進まないと思ったからです。
権利関係は問題の内容が難しいのですが、一度理解してしまえば暗記をしなくても解ける問題も沢山あります。
一方、法令上の制限・税その他は、用途規制の問題のように、工夫して数字を覚えないと解けない問題も出てきます。
そのため、まずはテキスト⇔過去問の往復のサイクルを繰り返し、暗記すべき知識をテキストに記録して絞り込んでいきました。
そして直前期には、テキストの重要知識を何度も見返し、それらを問題演習のアウトプットを通じて思い出すようにして、知識の定着を図っていきました。(良かった点③)
直前期の学習に要した期間
直前期1カ月間の学習において、約160時間を要することになりました。
これまでの学習時間を加味すると、宅建試験のトータルの学習時間は、約510時間となっています。
本試験、44点一発合格
今まで述べてきた勉強法を取り入れた結果、2024年度の宅建試験の本試験では、44点で一発合格を果たすことができました。
得点の内訳は、権利関係が10/14、宅建業法が19/20、法令上の制限・税その他が15/16となっています。
良かった点
①テキストをカスタマイズしたこと
宅建のテキストは、受験のプロである資格スクールがそれまでに培った受験ノウハウを生かして作り上げたものであり、テキストに掲載されているまとめ表の知識からの出題頻度も高くなっています。
実際に、本試験では、LECの「出る順宅建士 合格テキスト」の基礎知識が分かれば解ける問題だけでも35問が出題されており、それだけでほぼ合格レベルに到達することが分かります。
このテキストを存分に活用するためには、過去問のフィルターを通し、テキストにマーカーを引いたり補記を加えたりという、テキストをカスタマイズする方法がとても有効なのです。
この方法は、テキストをアレンジするだけなので、問題集に知識を書き足していく方法とは違い、どのレベルの受験生でもできる再現性の高い方法です。
私もこの方法を取り入れたことで、効率的に基礎知識を定着させることができ、宅建試験の合格を掴み取ることができました。
②年度別過去問や模試を正しく活用したこと
基礎知識の定着には、分野別過去問題集を解くことが有効です。
その後に、年度別過去問や模試に取り組むことになりましたが、ここでは余計な知識は入れず、これまでの基礎知識の確認と現場思考の訓練という2つの目的に絞って学習を進めました。
この方法を取り入れることで、基礎漏れを防ぎながらも、初見の問題への対応力を強化することができました。
③直前期に暗記中心の学習を行ったこと
宅建の学習を進めていく上で得た知識は、自分が思っている以上に不正確なものです。
自分では理解したつもりになっていても、初見の問題を解いた際にボロが出て間違いに気づくということもよくあります。
学習の前半期の過去問周回1週目~2週目の知識であれば、やむを得ないことでしょう。
それならば、この時期に徹底的な暗記をすると、間違った知識を強引にインプットしてしまう可能性が出てきます。
加えて、全体像を把握していないため、ムダな知識を覚えてしまうかもしれません。
正確な知識を、必要な分だけ覚えるという目的においては、直前期に暗記中心の学習を行ったことが極めて有効でした。
反省点
①無節操にマーカーを引いていた
クレアールの通信講座を受講している際に、基本講義の動画を視聴しながら、重要だと思う個所に所構わずマーカーを引いてしまいました。
その後、テキストのカスタマイズを行った際に、マーカーだらけになってしまい、復習する時には何とも読みにくいテキストになってしまいました。
マークする箇所は、講師の指示があった場合を除き、過去問のフィルターを通して得た知識だけに絞った方が、テキストも見やすくなりますし、覚えるべき点を整理できるようになると思います。
まとめ
以上の通り、この記事では私の取り入れた勉強法をまとめてみました。
宅建試験においては、テキストに載っているレベルの基礎知識が、これまでとは手を変え品を変えアレンジを加えた状態で出題されます。
これらの問題を取りこぼさないことが、合格への近道となっています。
そのため、①テキストの基礎知識をしっかり暗記すること、②現場思考のスキルを身に付けること、この2つがとても大切なのです。
この2つを実現する上で、私の取り入れた勉強法には一定の有効性があると思っています。
特に、テキストをカスタマイズするという方法は、どの受験生にも勧められる再現性の高い方法なのではないでしょうか。
今後、宅建試験の受験を検討している方は、是非とも参考にしてみてください。