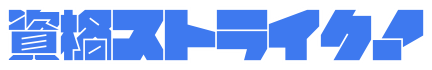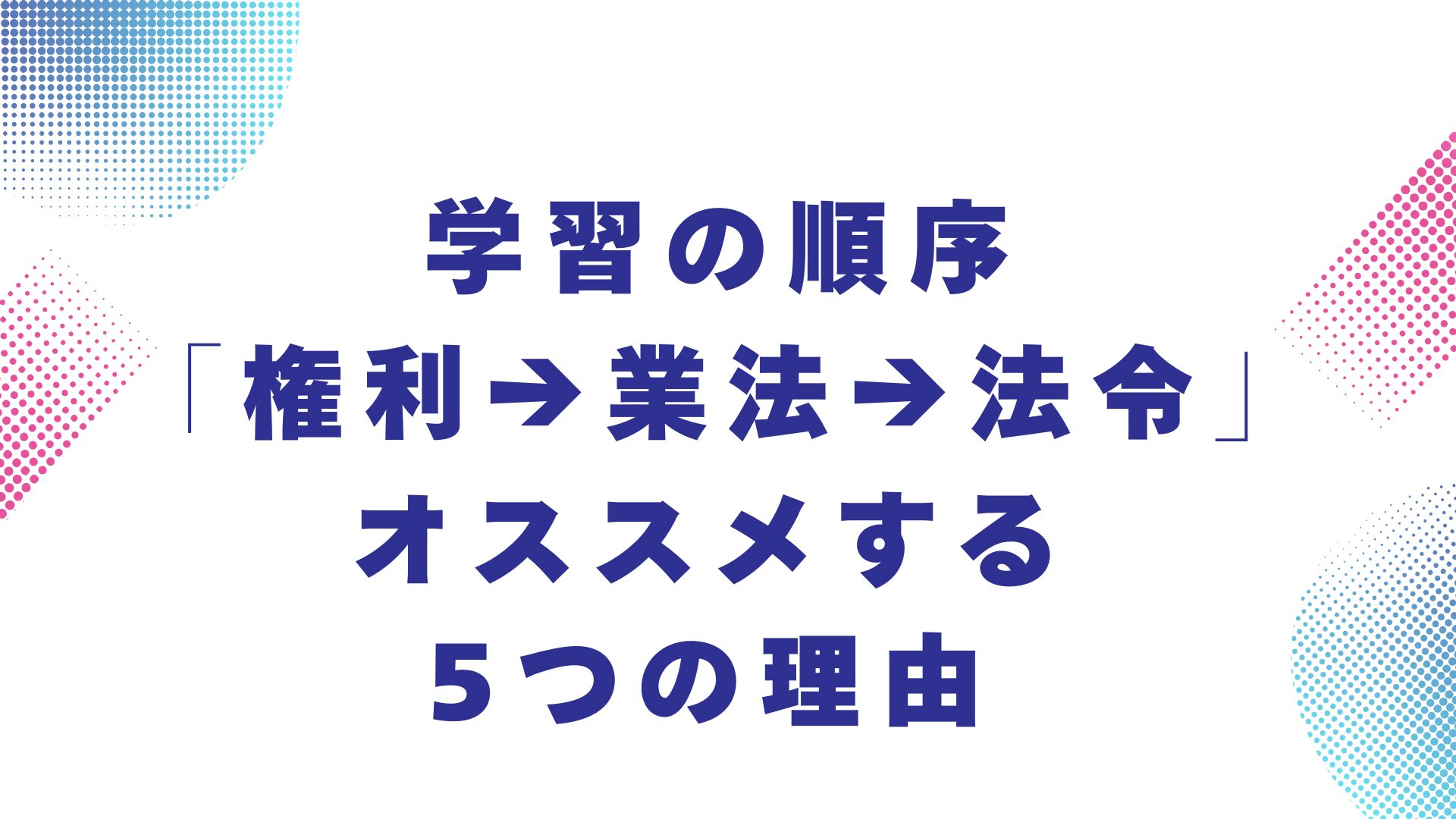こんにちは。私は当ブログの管理人、ぞねぞうと申します。
私は、R6年度宅建試験に挑戦し、44点で一発合格を果たすことができました。
その私がやっていたことは、クレアールの通信講座を受講し、LECの出る順宅建士シリーズの独学も行い、予想模試も複数社の問題を解くなど、「とりあえず何でも試してみる」という実験的な勉強法でした。
そのような経験を通じ、私は宅建の勉強法についていろいろなことを発見していきました。
そこで分かったことの1つは、科目の学習の順序は「①権利関係→②宅建業法→③法令上の制限・税その他」がオススメだということです。
その理由について、この記事で詳しく解説していきたいと思います。
「オススメの順番」「オススメしない順番」その理由
これから宅建試験を受験する方は、試験科目については「①権利関係→②宅建業法→③法令上の制限・税その他」の順番で学習を進めることをオススメします。
逆に、最もオススメできないのが、「①宅建業法→②法令上の制限・税その他→③権利関係」という順番です。
今から、その理由を述べていきます。
理由①:権利関係は「理解」科目、法令上の制限は「暗記」科目
「権利関係」、特にその中の「民法」という分野は、内容が難しく理解するのに時間がかかり、なおかつ範囲も膨大であることから、受験生を一番苦しめる分野です。
受験勉強で例えると、「数学」に近い科目です。
「数学」は内容を理解するまでが大変なのですが、いったん理解して問題が解けるようになれば、その内容を覚えておくことはそれほど難しくありません。
「何故その答えになるのか」について論理的に説明できること、つまり、理屈付けができることは記憶にも残りやすいのです。
「民法」もまったく同じであり、最初は大変なのですが、一度その内容を理解してしまえば、「宅建業法」や「法令上の制限・税その他」に比べて暗記する項目も少ないことから、その後の負担は軽くて済みます。
「民法」の場合、適切なメンテナンスをしていれば、理解した内容を本試験まで覚えておくことは難しくありません。
そのため、「権利関係」は一番最初に学習した方がいいのです。
一方、「法令上の制限・税その他」は「世界史・日本史」にも似た暗記科目であり、暗記したことは忘れやすく、記憶の維持をするためには、かなりの労力が必要となります。
そのため、「法令上の制限・税その他」は一番最後に学習して、忘れないうちに本試験に突入した方がいいということになります。
理由②:「コストの三重苦」を避けよ!
ビジネスの世界では、「イニシャルコスト」と「ランニングコスト」という用語がよく使われます。
日本語で言うと、イニシャルコスト(initial cost)とは「初期費用」「導入費用」のことであり、ランニングコスト(runnnig cost)は「維持費用」のことです。
例えば、コピー機本体の購入費用はイニシャルコストであり、トナー代や業者の点検費用はランニングコストということになります。
また、コストとは、お金だけでなく、「時間」のことを指すこともできます。
宅建試験に当てはめると、イニシャルコストは「学習内容を理解するのにかかる時間」となり、ランニングコストは「理解した内容を記憶しておくのに必要な時間」ということになります。
そこで、宅建試験の各科目に必要なコストの量をざっくりと表現すると、以下のようになります。
| 科目 | イニシャルコスト | ランニングコスト |
| 権利関係 | 大 | 小 |
| 宅建業法 | 中 | 大 |
| 法令上の制限・税その他 | 小 | 大 |
「権利関係」は、内容を理解するまでが大変なのですが、知識のメンテナンスにかかるコストは少なくて済みます。
「宅建業法」は、内容を理解するのは権利関係ほど難しくはないのですが、細かい事項の暗記が必要であり、知識のメンテナンスはとても大変です。
「法令上の制限・税その他」は、暗記中心の科目であり、「宅建業法」と同様に知識のメンテナンスにかかるコストが大きくなります。
まとめると、「権利関係」はイニシャルコストが大きく、「宅建業法」と「法令上の制限・税その他」はランニングコストが大きいのです。
そこで、「①宅建業法→②法令上の制限・税その他→③権利関係」という順番で学習を進めるとどうなるでしょうか。
「宅建業法」と「法令上の制限・税その他」の学習を終えた頃には、膨大なランニングコストを抱えていることになります。
その状態で、さらに「権利関係」のイニシャルコストの負担がかかってくることになります。
それぞれの科目のコストのピークが重なることで、三重の負担に苦しめられることになるのです。
学習内容の消化不良を起こし、下手をすれば学習を挫折してしまうかもしれません。
コスト分散の観点からも、「①宅建業法→②法令上の制限・税その他→③権利関係」という順番はあまりオススメできないのです。
理由③:権利関係は「時間が読めない科目」
私は新入社員だったころに、「時間が読めない仕事は前倒しでやれ!」と先輩から口酸っぱく言われたものです。
これは当たり前だけど、とても大事なことなんですよね。
このことを一日の仕事で例えてみます。
何時間かかるか分からない仕事は、午前中に取り掛かっていれば、時間が多少伸びたとしても定時までにはなんとか終わらせることがでしょう。
ところが、この仕事を午後から始めてしまうと、時間が延びれば最悪の場合は残業することになってしまいます。
就業間際には先輩も帰る準備をしているので、手伝ってもらうのも難しいかもしれません。
業務の残り時間が少なくなると、リカバリーの手段も限られてくるのです。
このことは、宅建試験でも同じです。
「権利関係」は「時間が読めない仕事」なのです。
特に、法律の初学者が独学をする場合、法律の基本的な考え方がまだよく分からないので、YouTube動画を何本もハシゴしてようやく理解する、ということもあるでしょう。
そうなれば、勉強時間は当初の見立てよりも大幅に増えることになります。
ただでさえ権利関係は範囲が広いので、YouTube動画のハシゴを繰り返していれば、全体の学習計画が大きく遅れるという事態にもなってきます。
こうなった場合でも、権利関係を一番最初に始めていれば、まだ本試験までには時間があるので、勉強時間を追加投入する等のリカバリープランを取ることができます。
ところが、権利関係を一番最後にしてしまうと、スケジュールが大幅に遅れた場合にリカバリーができなくなってしまうのです。
こうなれば、満足な直前対策もできず本試験を迎えるという最悪の結果になることもあります。
このように、受験生だけでなくビジネスパーソンの視点からも、権利関係は前倒しでやった方がいいと言えるのです。
理由④:最初に権利関係を学習すると法律の基礎が身に付く
「権利関係は内容が難しいから、一番最初に学習してはいけない」という意見がネット上で散見されます。
この意見については、私は賛同できません。
「宅建業法」や「法令上の制限・税その他」の後に「権利関係」の学習をしたとしても、「権利関係」の内容が理解しやすくなるとは思えないからです。
「宅建業法」や「法令上の制限・税その他」は暗記の比重が高い科目であり、考えさせる内容は少ないことから、「権利関係」の学習をする際には、あまりプラスに働かないのです。
一方、「権利関係」を最初に学習しておくことには大きなメリットがあります。
「権利関係」を学習するとことで、法的思考力が身に付くのです。
民法を取り扱うので、法律の考え方の基礎が分かり、その全体像が掴めるようになるのです。
全体が分かれば、部分を理解するのは容易になります。
「権利関係」を先に学習して法的思考力を身に付けておけば、後で学習する「宅建業法」や「法令上の制限・税その他」もスムーズに理解できるようになり、暗記もしやすくなるのです。
理由⑤:ほとんどの資格スクールが「権利スタート」
ネット上では「権利関係から学習を始めると挫折率が高くなる」という意見を耳にすることがありますが、本当でしょうか?
それではなぜ、多くの資格スクールでは、「権利関係」から学習をスタートさせているのでしょうか。
各スクールのホームページを確認しただけでも、以下の通りになっています。
「権利関係」から学習を始める資格スクール
- LEC
- TAC
- 日建学院
- 吉野塾
- みやざき塾
- アガルート
- 資格スクエア
- スタディング
- ユーキャン
- フォーサイト
ほとんどのスクールが、「権利関係」から学習を始めていることが分かりますね。
資格スクールとは、これまでに何万人もの受験生を合格に導いてきた、受験指導のプロフェッショナル集団です。
長年の指導で培われたカリキュラムには、確固たる根拠があるのです。
もし、「権利関係から学習を始めると挫折率が高くなる」ことが真実ならば、どの資格スクールも一番最初に「権利関係」の学習を始めるようなカリキュラムは作らないでしょう。
これから受験をする方は、安心して「権利関係」から学習を始めてください。
まとめ
この記事では、学習を進めるにあたり「①権利関係→②宅建業法→③法令上の制限・税その他」の順番をオススメする5つの根拠を挙げていきました。
逆に最もオススメできないのが、「①宅建業法→②法令上の制限・税その他→③権利関係」という順番であり、「短期合格狙いで権利関係は半分捨てる」という場合を除いて、この順番は避けた方がいいでしょう。
やはり、一番最初にじっくりと権利関係を攻略することが、合格への近道になるのです。