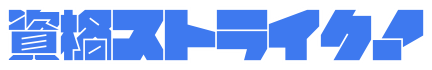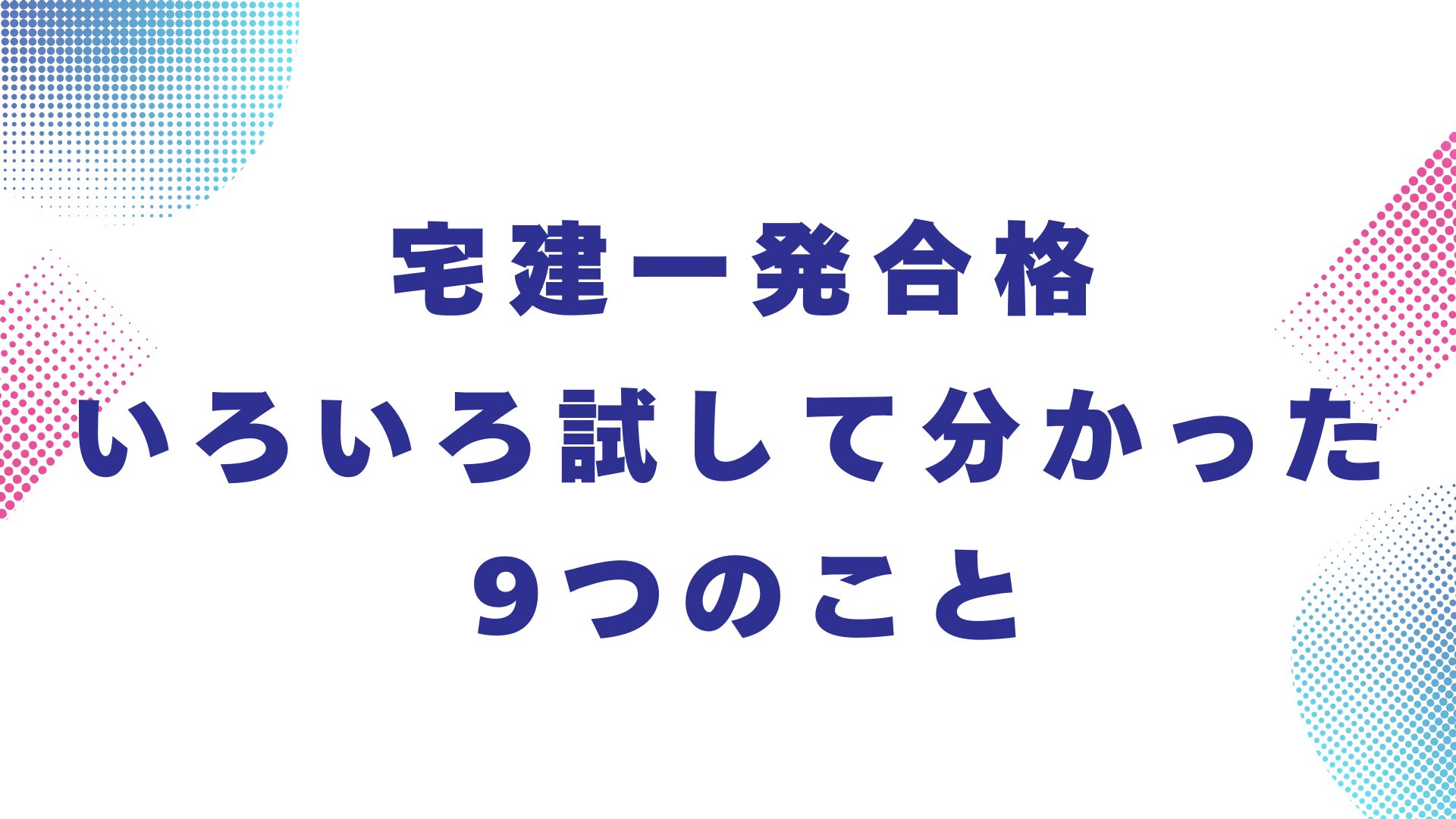こんにちは。私は当ブログの管理人、ぞねぞうと申します。
私は、R6年度宅建試験に挑戦し、44点で一発合格を果たすことができました。
その私がやっていたことは、クレアールの通信講座を受講し、LECの出る順宅建士シリーズの独学も行い、予想模試も複数社の問題を解くなど、「とりあえず何でも試してみる」という実験的な勉強法でした。
そのような経験を通じ、私は宅建の勉強法に関していろいろなことを発見していきました。
そこでこの記事では、自分の経験から分かったことについて、9つの項目を紹介していきます。
もちろん、勉強方法は人それぞれであり、私の経験は全ての人に当てはまるものではありません。
私の経験は、あくまでも1つの参考としてください。
いろいろな勉強法を試して分かったこと 9選
①テキスト&過去問の基礎知識が大切
私がやっていたことは、クレアールの通信講座を受講し、LECの出る順宅建士シリーズの独学も行い、さらに予想模試も複数社の問題を解くなど、本当にいろいろありました。
それでも、本試験で出題されたのは、テキスト&過去問の基礎知識にアレンジを加えた問題がほとんどだったのです。
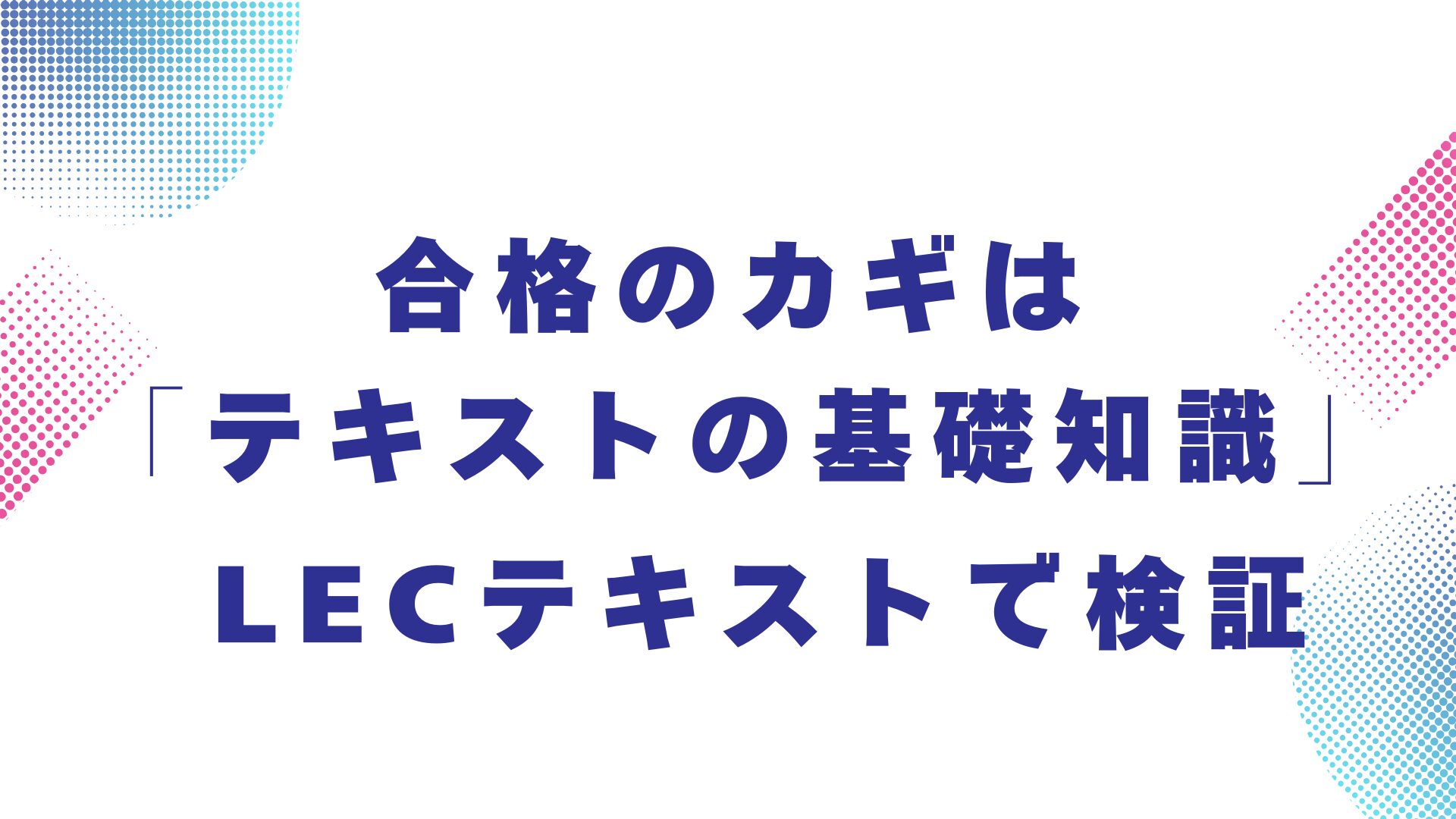
上記の記事でも検証した通り、「合格テキストのABランクの知識+ウォーク問のAランク問題の知識」で解ける問題だけで、38問も出題されています。
いかに基礎知識が大切かということがよく分かります。
あれこれと手を広げず、基礎をしっかりと固めることが合格への近道だったんですね。
②権利は最初に、法令は最後にやるべき
受験生時代は、「①宅建業法→②権利関係→③法令上の制限・税その他」の順番で学習を進めていたのですが、結構大変でしたね。
宅建業法で暗記した知識のメンテナンスをしながら、「権利関係(特に民法)」の難しい内容を理解していく、という2重の負担が重なり、学習を進めていくのにかなりの苦労を強いられていたのです。
民法は理解するまでがとても大変なのですが、いったん理解してしまえば、理屈付けができることなので、覚えたことが長期記憶に切り替わります。
知識を維持すること自体はそれほど労力がかかりません。
ところが、「宅建業法」「法令上の制限・税その他」は知識のメンテナンスにかなりの労力がかかります。
民法より先に手を付けてしまうと、2重3重の負担に苦しむことになるのです。
特に、「法令上の制限・税その他」はほとんど暗記科目なので、最後に回して忘れないうちに本試験を迎えた方がいいのです。
このことについては、以下の記事で検証しています。
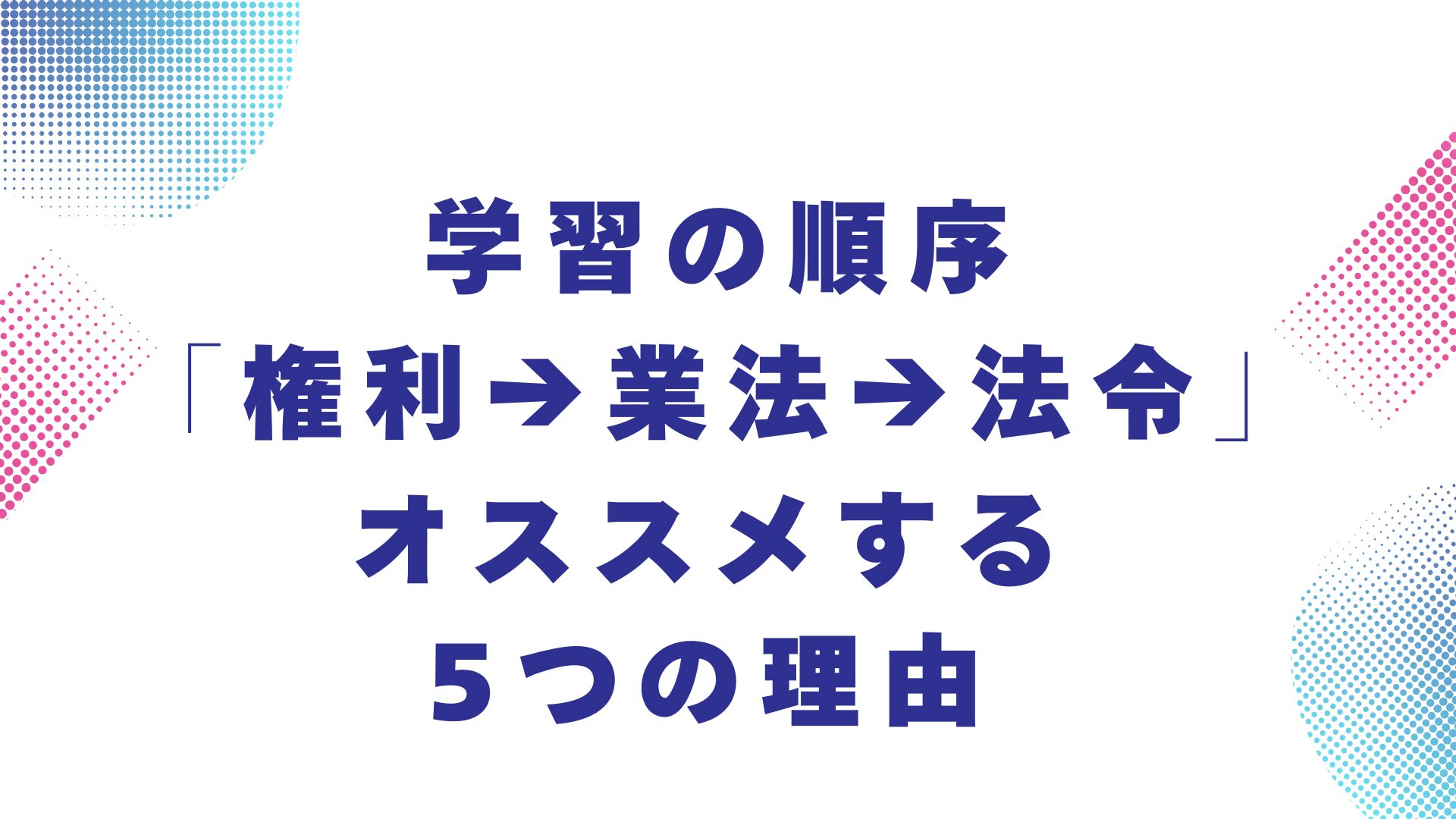
③情報はテキストに集約した方が良い。
宅建試験の受験勉強では、自分が得た知識を一元的に集約していくことがとても大切になります。
知識を集約する教材として、テキストと問題集の2つのうちどちらかを選ぶことになりますが、断然、テキストを選ぶことをオススメします。
問題集はあくまでもアウトプットツールであり、問題の解説が中心となっています。
一方、テキストには、問題を解く上での基本ルールが書かれています。
基本ルールさえ分かっていれば、問題文の表現を変えられた場合でも現場思考で対処することができます。
テキストは、この基本ルールが図解や表の形式で分かりやすくまとめられており、過去問の関連知識も確認しながら一緒に覚えることができるので、とても効率的なのです。
この基本ルールは、過去問を解く際に、解答の根拠となった箇所にマーカーを引いてあぶり出しをすれば、より明確になっていきます。
「過去問ではよく出てくるけど、テキストには載っていない」という基本ルールは、テキストに追記してもいいでしょう。
いずれにせよ、プロが作った教材にアレンジを加えるだけなので、誰にでもできる方法なのです。
一方、問題集の解説欄をアレンジし、それこそテキストレベルの教材に改造していくことは、高い編集スキルが求められる作業であり、誰にでもできることではないと思います。
④合格レベルの知識に絞れば短期合格は可能
私は本当にいろいろな勉強法を試したので、トータルの学習時間は510時間かかっています。
しかしながら、最初に公開模試を受けた時には44点を取れたので、その時点で合格レベルに達していたことになります。
その時点の学習時間は350時間であり、クレアール過去問3周+LECウォーク問2周の周回が完了している状態でした。
クレアールの通信講座が終わった後に、ゼロから始めるつもりでLECのテキストを読みつつウォーク問の周回を行ったため、それだけの時間がかかりました。
そのどちらかに集中していれば、勉強時間を300時間くらいまでは短縮できたと思います。
本試験ではテキスト&過去問の基礎知識が中心に出題されることを考えれば、この学習時間でも十分に合格レベルに達するのではないでしょうか。
⑤テキストは1冊で十分
受験生時代に、私は様々な合格体験談をネットで見ていました。
その中に、「LECのウォーク問+テキストだけで受かった」という体験談があり、私は思わず疑ってしまいました。
ところが、受験を終えた今では「そりゃそうだよね」と100%納得しています。
アレコレと手を出さず、1冊のテキストをベースに基礎知識を積み重ねていけば、十分に合格できることが分かったのです。
(参考記事:通信講座とウォーク問を両方やると、いくらかかった?)
「①テキスト&過去問の基礎知識が大切」でも述べた通り、テキストの基礎知識にアレンジを加えた問題が大量に出題されることを考えると、むしろ一つのテキストを徹底して仕上げていった方がいいのです。
当然、テキストは2冊も揃える必要は全くありません。情報が分散してしまうからです。
隣の芝生が青く見えるのかもしれませんが、今使っているテキストに書いていないことがあれば、情報を適宜補記していけばいいのです。
⑥やっぱり資格スクールの方が有利
スクールの発表する受講者の合格率は、軒並み50%を超えており、全体の合格率を大きく上回っています。
独学に比べて資格スクールが勝っている一番のポイントは、「余計な勉強をしなくて済む」ということです。
私はクレアールの通信講座を受講していましたが、講義の中で事あるごとに「出る/出ない」の仕分けをしてくれたので、とても助かりました。
資格スクールは、長年の指導経験に基づき出題傾向を徹底分析して、試験に出るところを中心に教えてくれるので、余計な勉強をしなくて済むのです。
一方、独学の場合だと、分かっているつもりでも、ついついCランクの知識まで手を広げるということがよく起こります。
カリキュラムが完全に自由だからこそ、情報のコントロールができなくなってしまうのです。
特に、権利関係などは学習範囲が広く、気が付けば「沼」の中にハマり込み、本当に大切な基礎が抜けていきます。
このように、余計な勉強をしなくて済むから、資格スクールの方が有利なのです。
⑦ただし、独学でも十分に合格できる
スクールの方が有利なことには変わりませんが、宅建試験は独学でも十分に合格できる試験です。
宅建試験では、テキスト&過去問の基礎知識が合格のカギを握っており、そこをしっかりと押さえておけば独学でも十分に戦えるのです。
何も、スクールでしか解説ができない難問が決め手となっているわけではありません。
LECの出る順宅建士シリーズを使うとしたら、「合格テキストのABランクの知識+ウォーク問のAランク問題の知識」といったような、教材のランク付けに従って粛々と学習を進めていけばいいのです。
カリキュラムが自由だからと言って、余計な情報には気を取られないことです。
情報のコントロールが自分でできるのであれば、スクール生とも互角に渡り合えるでしょう。
⑧「知識のドーナツ化」現象に注意
独学の場合に起こりやすいのですが、SNS等の情報に振り回されて不安になり、「あれもやらなきゃ」とCランクの知識にまで手を広げてしまいます。
私も一時期そうなったことがありますが、「Aランクの知識は最初にやっているから、Cランクをやれば他の受験生に勝てる!」と思い込むわけです。
この状態になるとどうなるか。
周辺にあるCランクの知識を追いかけるあまり、本当に大切なAランクの知識が抜け落ちてしまうのです。
いわば、「知識のドーナツ化」現象です。(これは、タレントの上岡龍太郎さんが作ったとされる言葉です。)
Aランクの知識で解ける問題を落とすことは、他の受験生に大きく引き離されることになり、宅建試験においては致命傷となってしまいます。
⑨予想模試は使い方次第
当たり前なのですが、本試験では初見の問題が出題されます。
過去問とは違った角度から知識が問われてきます。
正確な基礎知識と現場思考の能力を身に付けていないと正解できません。
予想模試も同様であり、予想模試を活用すればこの2つの能力が鍛えられることから、初見の問題への対応力が身に付くのです。
ただし、ヤマを当てるつもりで模試を受けまくり、その結果として基礎知識に抜け漏れが生じるのなら、模試を受けるコストパフォーマンスは極めて劣悪なものになります。
私は、クレアール1回、TAC1回、LEC4回、日建学院2回と、複数社の予想模擬試験の問題を解きまくっていました。
それだけの問題を解いても、明確に模試の知識で解けたという問題は1問に留まり、その他の大部分はテキスト&過去問の基礎知識でも解ける問題でした。
基礎知識をしっかりと維持してこそ、模擬試験を受ける意味が出てくるのです。
その目的を逸脱し、模試の知識(特にCランク)を新たに取り入れて得点アップを狙うとなれば、途端に効率が悪くなるのです。
まとめ
この記事では、いろいろな勉強法を試したことで分かった9つの事項について述べていきました。
ある意味回り道をしたからこそ、見えてきたことも多々あります。
勉強方法は人それぞれだと前置きはしつつも、この記事が宅建合格を目指す方の参考になればと思っています。